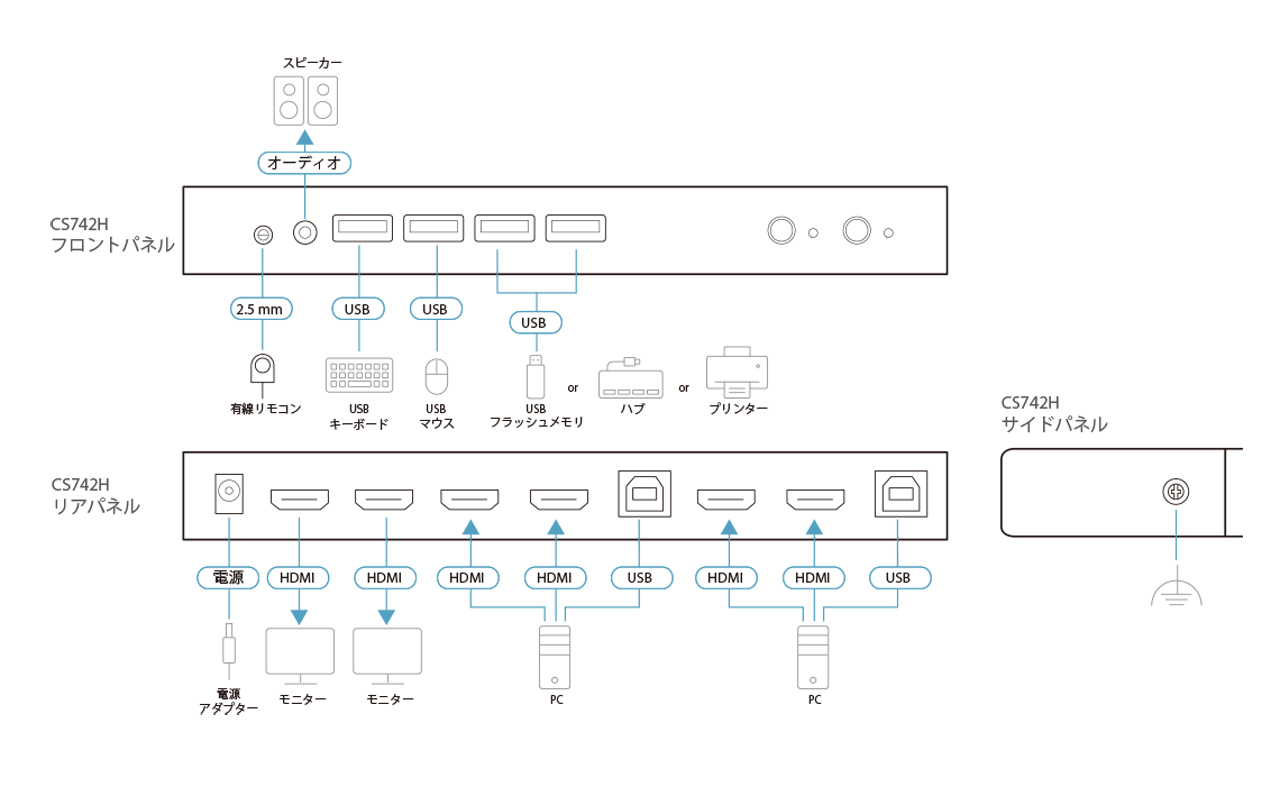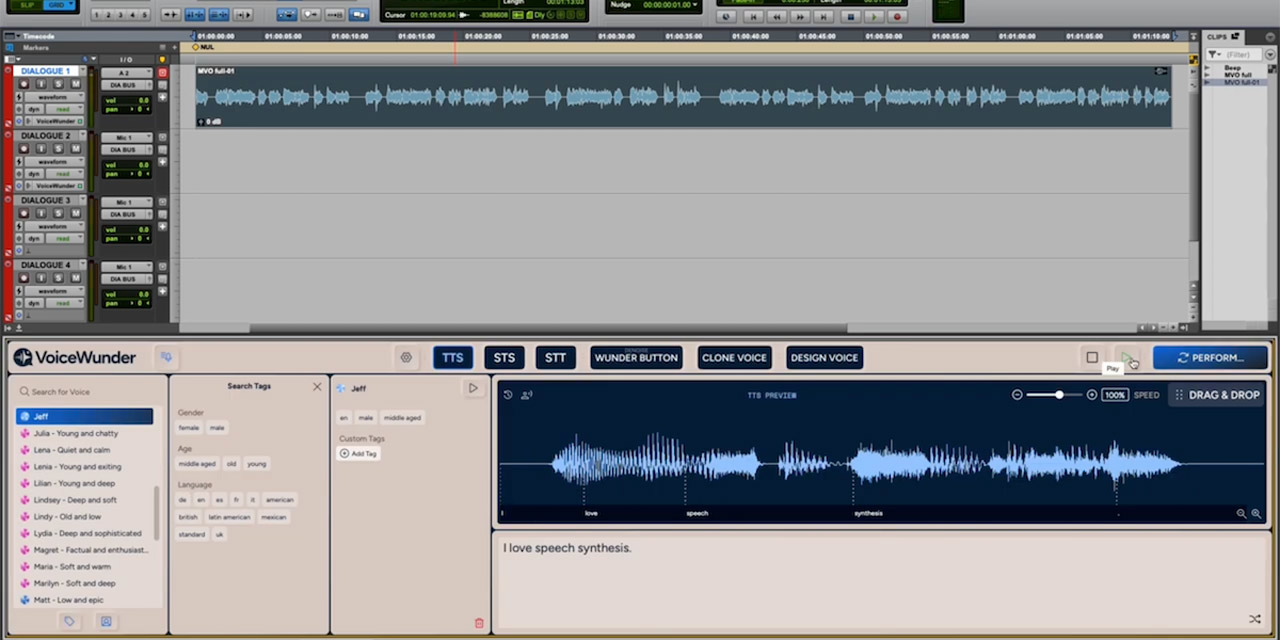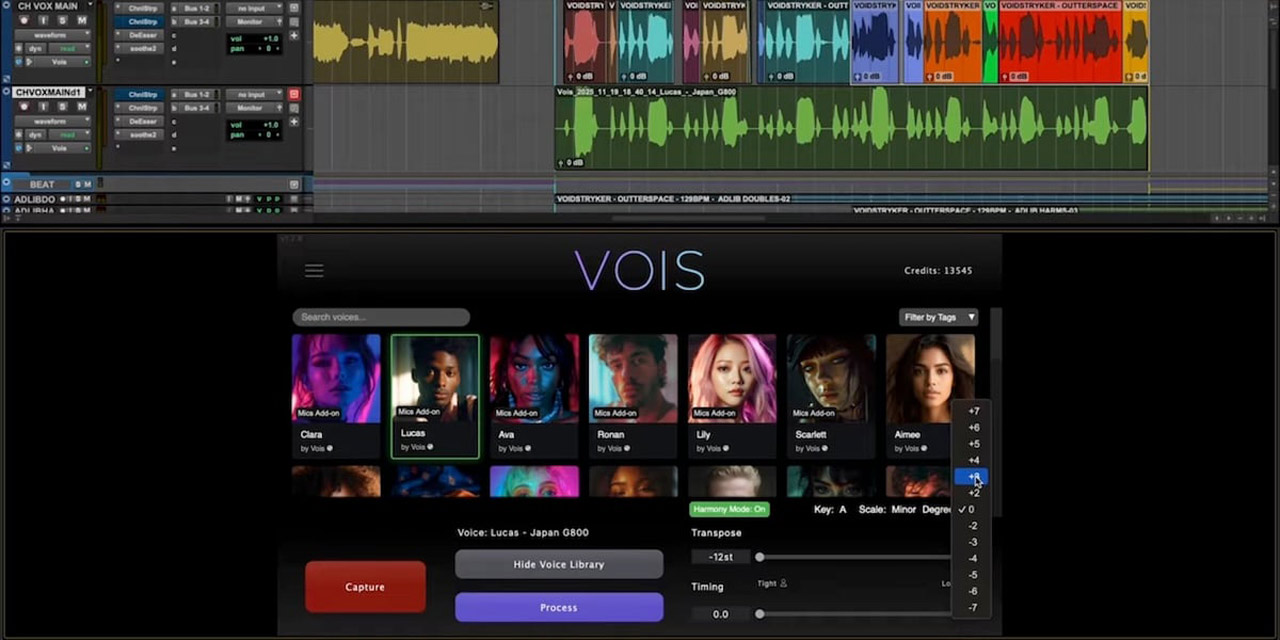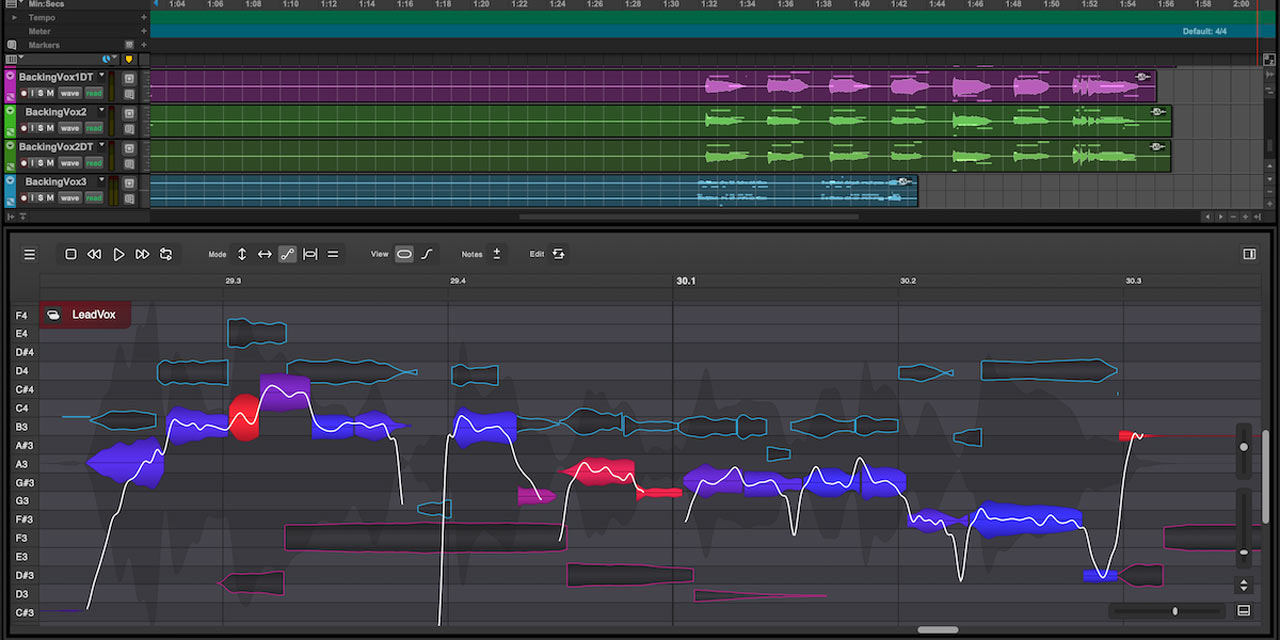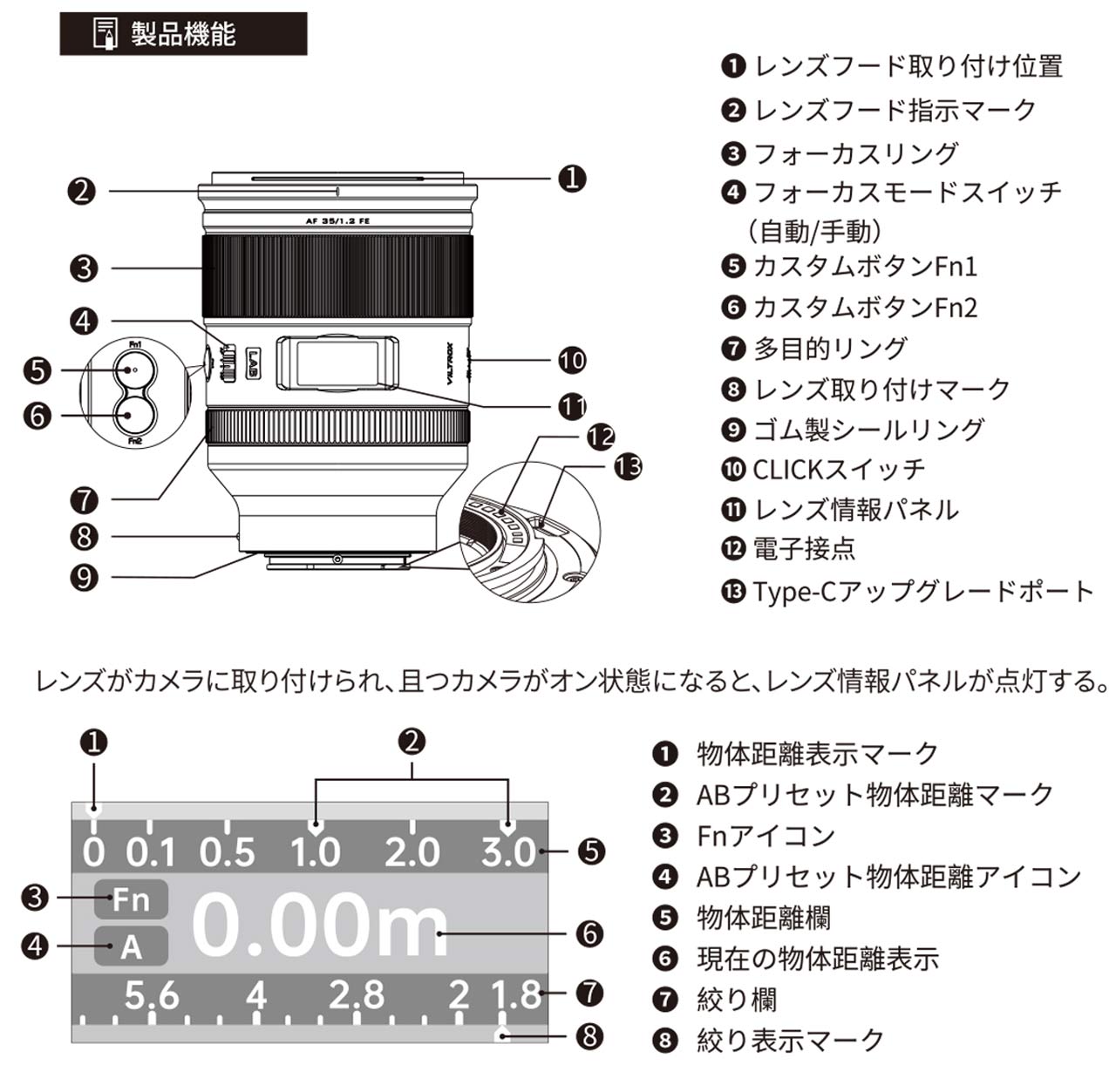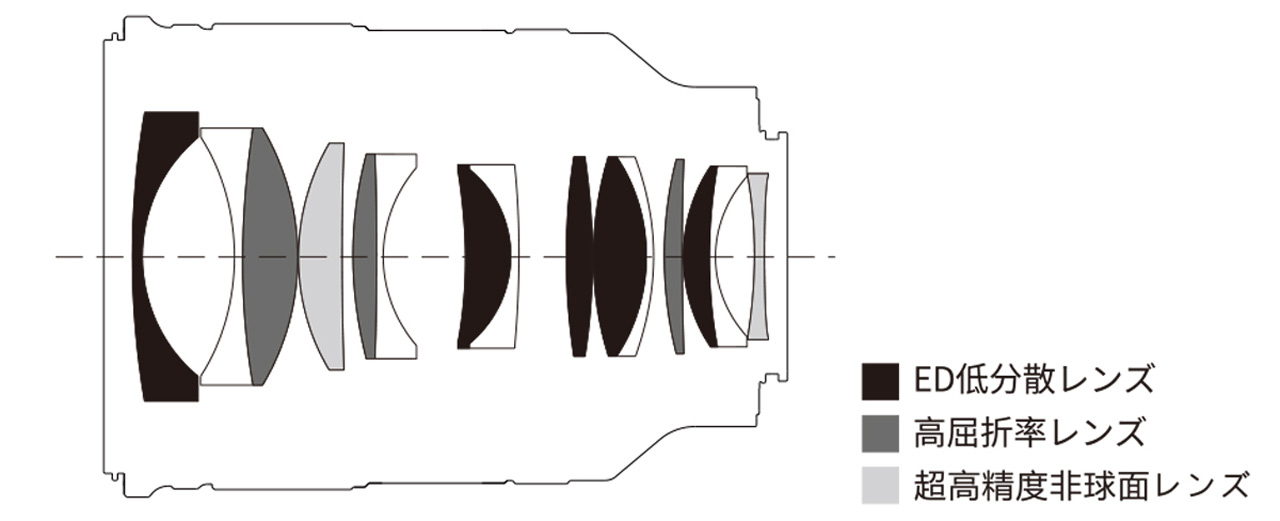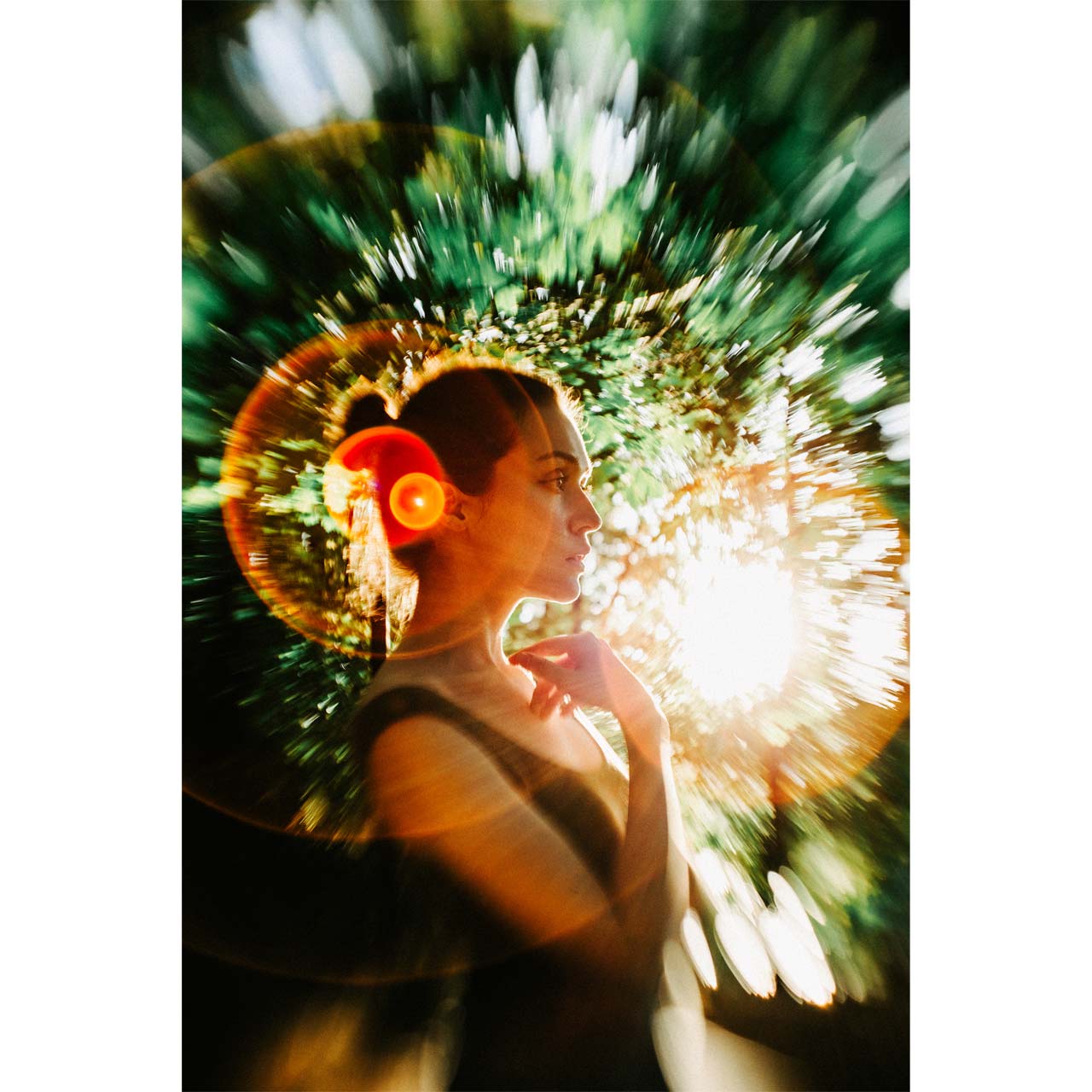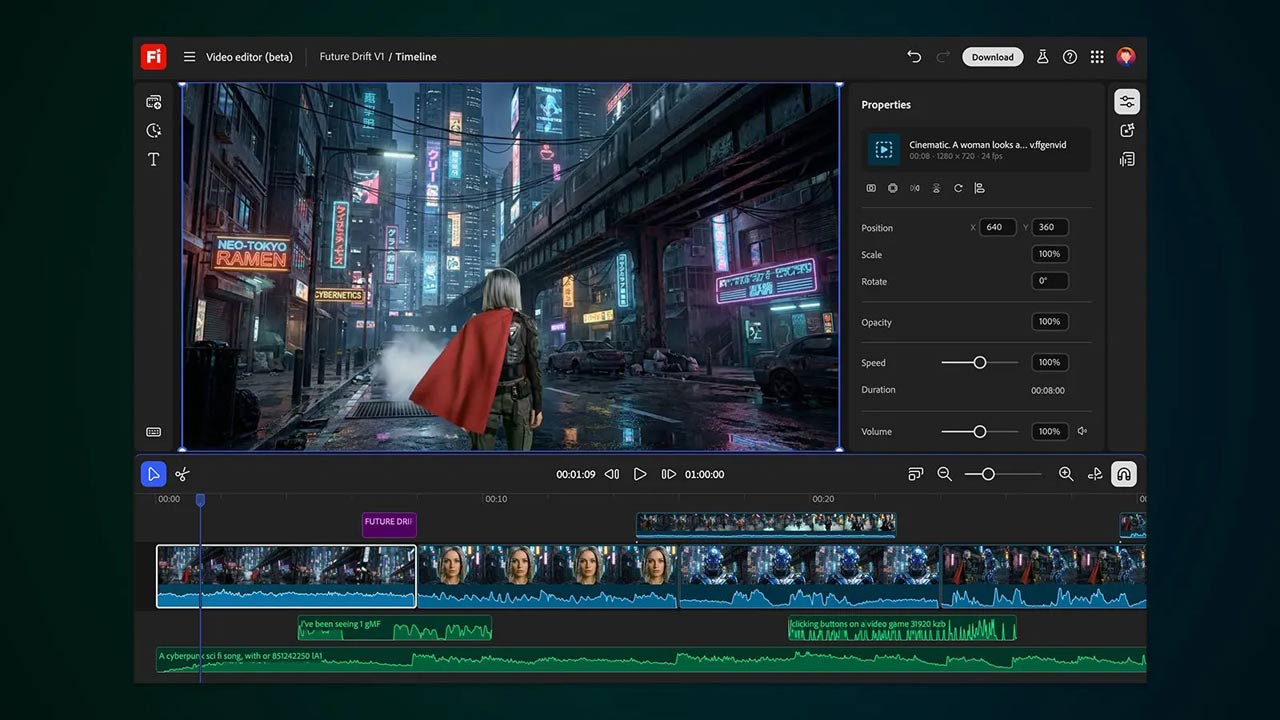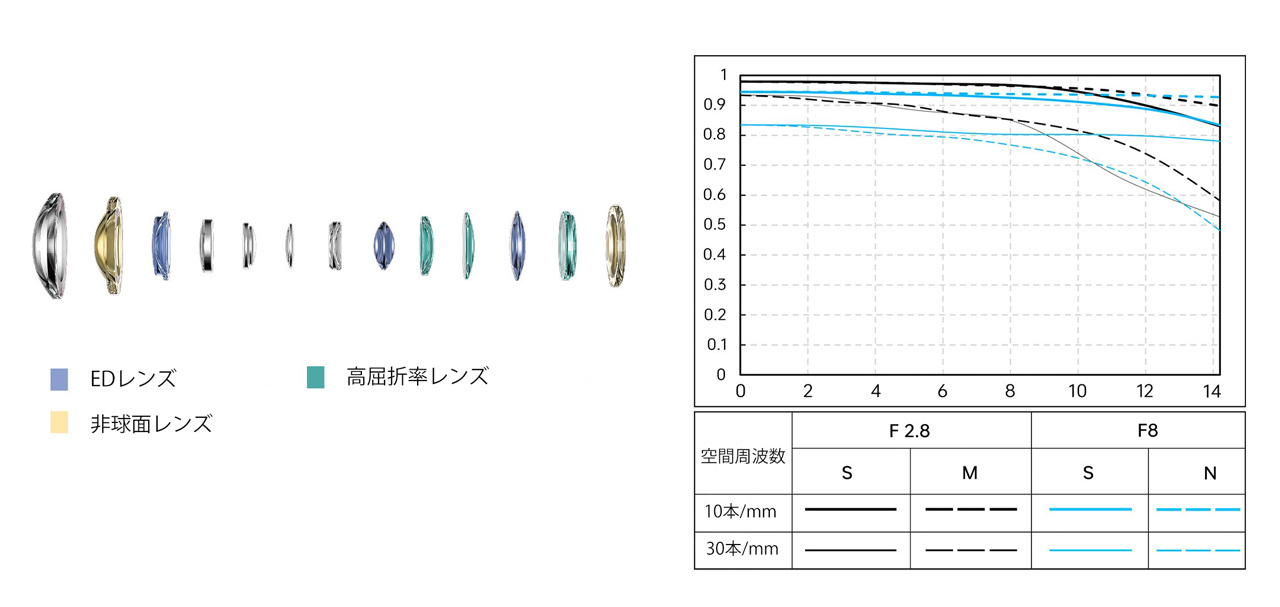PRONEWS AWARD 2025 レンズ部門におけるノミネート製品を俯瞰すると、2025年はレンズの価値軸そのものが大きく揺れ動いた一年だったことが見えてくる。高解像度化や大口径化といった従来の競争軸に加え、オートフォーカス化、軽量化、価格帯の再定義、さらには描写の「味」への再評価など、複数の潮流が同時進行した年であった。
本稿では、各ノミネート製品をこれらの価値軸のいずれかを代表する存在として位置づけ、その意義を読み解いていく。
まず、2025年を象徴するトレンドとして挙げないわけにはいかないのが、「アナモフィックレンズのオートフォーカス(AF)化」だ。その筆頭として選出したのが、SIRUI「40mm & 20mm T1.8 S35 1.33x」アナモルフィックレンズである。これまでマニュアルフォーカスが常識だったアナモフィックの世界に、S35/APS-C対応かつAF駆動という新たなスタンダードを持ち込んだ意義は大きい。T1.8という明るさを確保しながら、40mmモデルで約614gという軽量コンパクトな筐体に収めた技術力には素直に驚かされた。マウントは、E、MFT、Z、Xマウント対応で、ワンマンオペレーションの現場を深く理解した設計であり、「アナモフィックはMFが常識」という固定観念を覆し、この分野における価値観の転換を強く印象づけた一台である。
シネマレンズにおけるAF化という潮流は、シグマ「AF Cine Line」によって、さらに明確な輪郭を与えられた。「28-45mm T2 FF」および2026年春発売の「28-105mm T3 FF」は、硬派なマニュアル操作が主流だった同社シネラインに、リニアモーターHLAによる本格的なAFを導入した点が大きな特徴だ。
写真用レンズで培った光学性能を土台としつつ、クリックレス絞りやギアはシネマスタンダードの0.8Mピッチなど、筐体は完全にプロフェッショナルなシネマ仕様へと刷新されている。
写真用AF技術と本格シネマ筐体を両立させることで、AFシネレンズを「妥協の選択」ではなく、現実的な制作ツールとして再定義する可能性を示した。
一方で、シグマがハイエンド市場に向けて投入した「Aizu Prime Line」は、その仕様を見ただけでも強い意志を感じさせるシリーズだ。
φ46.3mmという広大なイメージサークルと全焦点距離でのT1.3統一、さらに現代のVFXワークフローを強く意識した設計である。ZEISS eXtended Dataへの対応を含め、光学性能だけでなくシステムとしての完成度も高く、日本発のシネマレンズがハイエンド領域において十分に競争力を持ち得ることを具体的に示した。
今年はまた、「性能」一辺倒ではなく、「味」を積極的に取り込む動きも際立っていた。Tokina「Vista-C」シリーズは、現代的なT1.5の明るさと解像力を維持しながら、あえて周辺解像度を落とし、赤や青のフレアが出やすいヴィンテージ的な特性を注入してきた。計算された「崩し」による有機的なルックは、高解像度時代におけるクリエイターの渇望に応えるものであり、高性能・高解像度一辺倒の流れに対して、「意図的な崩し」という価値を、明確な意志をもって提示した一本である。
同様に、Leitz「HEKTOR」シリーズも印象深い。往年の名玉へのオマージュを込めつつ、交換可能なミラーレスマウントを採用するという大胆な戦略は、同社の覚悟を感じさせるものだった。
Leitz Cine製のレンズが、ミラーレス世代のユーザーにとって現実的な選択肢として手の届く位置に近づいたことを、強く印象づける出来事であった。
効率や自動化が進む市場において、描写と操作性を最優先に据えるという価値観を改めて可視化した存在と言える。
コストパフォーマンスと機能のバランスという観点では、DZOFILM「Vespid 2」が放ったインパクトも大きい。1本あたり20万円以下というエントリークラスの価格帯でありながら、Cookeの「/i Technology」によるメタデータサポートを実装し、全域T1.9で統一してきた仕様は極めて野心的だ。エントリー価格帯であっても妥協なき機能統合が可能であることを明確に示し、シネレンズ市場における従来の前提に再考を促した存在である。
価格帯による序列そのものに疑問を投げかけた点も、本シリーズの重要な意義と言える。
特殊撮影の分野では、LAOWAの新型プローブズームレンズ「15-35mm T12」および「15-24mm T8」の進化が光った。従来は画角調整のたびにカメラごと移動する必要があったプローブレンズにズーム機構を搭載したことで、撮影効率は飛躍的に向上している。
モジュール式による形状変更の柔軟性も含め、プローブレンズを「特殊機材」から、現場で使われる実用的な撮影ツールへと位置づけ直した一本である。
マクロ撮影や特殊撮影を限られた用途から解放し、より日常的な表現手法へと引き寄せた点で、市場の使われ方そのものに影響を与えた。

※画像をクリックして拡大
こうしたレンズ観の変化は、シネマレンズの世界にとどまらず、スチルと動画を横断するハイブリッドな領域にも確実に波及している。
スチルと動画の垣根を越えるハイブリッド領域において、ニコンの「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」は、完成された存在と見なされてきた標準ズームというカテゴリーに、改めて問いを投げかけた一本である。
インナーズーム化と大幅な軽量化を同時に実現した本レンズは、単なる改良型にとどまらず、ジンバル運用やワンマンオペレーションを前提とした現代的な撮影スタイルに対する、明確な回答を示している。特に注目すべきは、ズーム操作による重心変化を排した設計思想だ。これはスペック上の進化ではなく、撮影現場での判断や段取りそのものを簡略化する実用的な価値をもたらす。
標準ズームという“完成形”と思われていた領域において、運用面から再定義を行った点で、本レンズは2025年のレンズ価値軸の変化を象徴する存在の一つと言える。
キヤノンの「RF45mm F1.2 STM」は、価格帯の再定義と軽量化を同時に成立させた価値軸を明確に示した一本だ。
F1.2という極端な大口径を掲げながら、400gを切る軽量ボディと現実的な価格帯を両立させた本レンズは、「大口径=特別な機材」という前提を大きく揺さぶっている。
従来、F1.2クラスのレンズは、描写と引き換えに重量や取り回しを受け入れる存在だった。しかし本レンズは、動画撮影や日常的な運用を視野に入れたSTM駆動と軽量設計によって、大口径表現を“特別な選択”から“日常的な選択肢”へと引き寄せた。
表現力と現実性の両立という観点で、ミラーレス時代のレンズ設計思想の転換を明確に示した存在である。
さらに、APS-C用標準ズームレンズシグマ「ART 17-40mm F1.8 DC」は、かつての名玉「ART 18–35mm F1.8 DC HSM」を現代的な軽量ボディと最新マウントで蘇らせ、動画制作者に新たな選択肢を提示した。
ZEISS「Otus ML」シリーズは、効率化やAF化とは距離を取り、描写の純度と撮影者の意思を最優先するという価値軸を担った存在だ。AF化や効率化が急速に進む市場環境の中で、本シリーズは「撮るという行為」そのものへの覚悟を、真正面から問いかけてきた。
究極的な光学性能と引き換えに、操作の自動化を一切排した設計は、決して万人向けではない。しかしだからこそ、表現に対して主体的であろうとするクリエイターにとって、本シリーズは代替不可能な存在となる。
過去の名作を単に再現するのではなく、ミラーレス時代においてもなお“撮影者の意思”を最優先に据えるという選択肢が成立することを示した点で、Otus MLは2025年のレンズ群の中でも、異質かつ象徴的な存在であった。
総じて、今年のノミネート製品は、単なるスペック競争を超え、撮影スタイルや表現の幅を具体的に拡張する力を備えたものばかりであった。それぞれのメーカーが提示した「次世代のレンズ像」に、心からの敬意を表したい。
本年度のノミネート製品は以下の通りである。
- SIRUI「40mm & 20mm T1.8 S35 1.33x」アナモルフィックレンズ
- シグマAF Cine Line「28-45mm T2 FF」
- シグマ「Aizu Prime Line」
- トキナー「Cinema Vista-C」
- ライツ「HEKTOR」
- DZOFILM「Vespid2」
- LAOWA「15-35mm T12 / 15-24mm T8」
- ニコン「NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II」
- キヤノン「RF45mm F1.2 STM」
- シグマ「ART 17-40mm F1.8 DC」
- ZEISS「Otus ML」
PRONEWS AWARD 2025 レンズ部門 ゴールド賞
シグマ「ART 17-40mm F1.8 DC」

ゴールド選定理由|「現場を動かした一本」
ここからは、数あるノミネート製品の中でも、2025年の映像制作ワークフローに最も直接的な影響を与えた一本として、ゴールド賞に選出した理由を述べる。評価の軸としたのは、レンズの思想や方向性ではなく、実際の現場における判断と運用をどれだけ更新したかという一点である。
PRONEWS AWARD 2025 レンズ部門ゴールドは、シグマAPS-Cミラーレス用ズームレンズ「ART 17-40mm F1.8 DC」を選出した。写真用ズームレンズでありながら、動画撮影の現場において事実上の“標準レンズ”として機能した点を高く評価した。
本レンズは、かつて多くの映像制作者に支持された「ART 18–35mm F1.8 DC HSM」の思想を継承しつつ、焦点距離の拡張と大幅な軽量化、さらにミラーレス専用設計へと進化を遂げている。これにより、一眼レフカメラマウント時代から移行をためらっていた制作者に対し、運用面での明確なメリットを提示した。レンズ交換の頻度、ジンバル運用時のバランス調整、ワンマンオペレーションにおける負担といった、日常的な制作判断の前提を確実に書き換えた点は見逃せない。
また、F1.8通しというスペックがもたらす表現力を、特別な機材や高価なシネレンズに頼らず実現できる点も重要だ。描写性能、取り回し、価格のバランスが極めて現実的であり、同社公式ストアで148,500円(税込)という価格設定も含め、多くの現場に「選ばれる理由」を持ったレンズであった。
2025年において、実用性と影響力の両面で最も多くの制作現場を動かした一本であり、ゴールド賞に選出するにふさわしいと判断した。
PRONEWS AWARD 2025 レンズ部門 シルバー賞
Leitz ミラーレス用シネレンズシリーズ「Cine HEKTOR」

シルバー選定理由|価値観を揺さぶった挑戦
シルバー賞では、撮影現場を即座に変える実用性や合理性とは異なる次元で、映像制作における価値観そのものを問い直したレンズを選出した。効率化やAF化、軽量化といった進化軸が加速する中で、本賞は「描写とは何か」「撮るという行為に、どこまで撮影者の意思を残すのか」といった根源的な問いを、現代の制作環境において提示した存在を評価する枠である。
PRONEWS AWARD 2025 レンズ部門シルバーは、Leitz Cineのミラーレス用シネレンズシリーズ「Cine HEKTOR」を選出した。本シリーズは、合理性や効率性を最優先とする現在の潮流とは距離を取り、描写の個性や撮影者の意思介在を重視するという、明確な思想を製品として提示している。
特筆すべきは、その思想を単なる理念にとどめず、ミラーレス対応と交換可能マウントという具体的な設計に落とし込み、現代の制作環境において“選択可能な現実解”として成立させた点だ。Cine HEKTORは、広く使われるためのレンズではない。しかし、映像制作が何を大切にすべきかを改めて考えさせる力を持った存在として、2025年のレンズ観に確かな揺さぶりを与えた。その点を高く評価し、シルバー賞に選出した。