
ソニーが示す、映像制作現場における空間コンテンツの未来
Inter BEE 2025のソニーブースで上映される映像作品「Laundry」の制作現場を取材した。本作は、VENICEエクステンションシステムMiniによる空間コンテンツ撮影と、空間再現ディスプレイ技術を組み合わせた検証プロジェクトである。ソニーが目指す新しい映像体験の方向性を、具体的な撮影とディスプレイ運用を通して示す試みでもある。
VENICEエクステンションシステムMiniは、ヘッド部が既存モデル比で約70%小型化されたカメラシステムである。コンパクトで軽量な設計により、手持ち撮影や小型ジンバルへの搭載、狭い空間への設置など、運用の自由度が大きく広がった。2台を横に並べた際のセンサー中心間距離は約64mmで、人の瞳孔間距離に近い。この構成により、自然な立体感を持つステレオ撮影が行える。

ソニーが提唱する「空間コンテンツ制作」は、従来の3DやVRの延長線上にある技術ではない。現実の空間を高い精度で再現し、その場にいるかのような体験をつくり出すことを狙ったアプローチである。ラスベガスの「Sphere」のように、空間全体を表現のキャンバスとして扱う発想に近い。
ソニーは2025年6月のCine Gear Expo 2025で75インチの大型空間再現ディスプレイを参考展示し、その没入感は多くの来場者に強い印象を残した。さらに、ミラーレスカメラで撮影した画像から高品質な3Dアセットを生成するクラウドサービス「XYN(ジン)空間キャプチャーソリューション」も展開している。
同ソリューションのモバイルアプリケーションは撮影状況をリアルタイムに可視化し、効率的な撮影を支援する。こうした技術群は、クリエイターの視点や制作ツール、作品の提示方法に変化を促し、「空間コンテンツ」という新たな表現領域の拡大を後押ししている。


今回の撮影現場で確認した技術、とりわけ空間再現ディスプレイは、インダストリアルデザイン用途に留まらず、空間コンテンツ映像制作のワークフローそのものを変革しうるポテンシャルを持つ。
このコンテンツのポイントは、撮影中に空間再現ディスプレイで立体映像をリアルタイムモニタリングできる点にある。カメラマンやディレクターは、その場で立体感やバランスを確認できるため、従来の3D制作のようにポストプロダクションで初めて破綻に気づく、といったリスクを大きく減らせる。
さらに、裸眼での立体視を実現していることも重要だ。VRゴーグルを用いた立体視は一般的になりつつあるが、ゴーグル不要のシステムは、より自然でハードルの低い3D体験を提供する。空間再現ディスプレイが今後どの分野で力を発揮し、どのような新しい映像体験をもたらすのか、動向が注目される。
ソニー技術陣が結集:「Laundry」で挑む新たな映像表現
撮影現場は千葉県八千代市の「コインランドリーひまわり」。店内を貸し切った撮影には、ソニーの各部門から多くのエンジニアやスタッフが集まっていた。今回の撮影が単なるプロモーションではなく、技術開発の重要な試みとして位置付けられていることがわかる。

現場には、CineAltaラインの「VENICEエクステンションシステムMini」関連チーム、空間再現ディスプレイ開発チーム、XRチームのメンバーが集結。XRチームは、CES 2025で発表された空間コンテンツ制作ブランド「XYN(ジン)」に含まれる空間キャプチャーソリューションやモバイルモーションキャプチャー「mocopi」などを手がけており、リアルタイムモニタリングシステムの構築をサポートしていた。
コインランドリー内は日中の太陽光を暗幕で完全に遮断し、徹底的にコントロールされたナイトシーンが作り出されていた。
「Laundry」は、コインランドリーで偶然出会った男女が、光り出す洗濯機をきっかけに夢の世界へ誘われ、車中で踊る幻想的な時間を過ごした後、現実に戻るというファンタジー仕立ての物語である。セリフは一切なく、音響と映像のみでストーリーを紡ぐ。


この舞台設定の背景には、「VENICEエクステンションシステムMini」を2台並べた姿がコインランドリーの洗濯機に似ている、という撮影監督・会田正裕氏の着想がある。この視点が、コンセプトとビジュアルを自然に結びつけている。
最先端機材と革新的なワークフロー
撮影機材は、VENICEエクステンションシステムMini2台とVENICE 2が2台。Miniのヘッド部を並べ、その下段のカートにVENICE 2本体を収納する構成でステレオ撮影が行われた。8K60P収録により、空間再現ディスプレイでの表示を前提とした高精細な立体映像が得られている。
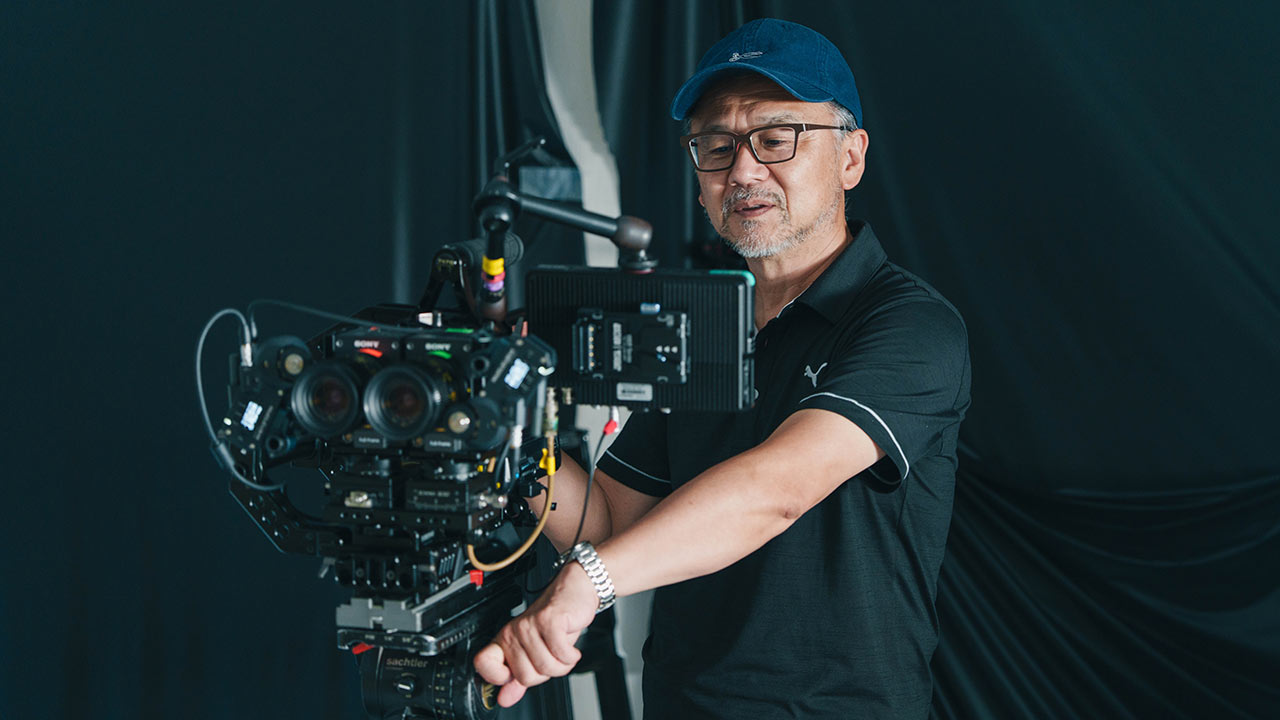

撮影現場では、27インチの空間再現ディスプレイ「ELF-SR2」がプレビューモニターとして使われた。カメラで撮影した映像は光ファイバーでベースステーションに送られ、そこでHDMI信号に変換してディスプレイへ入力する。この流れにより、撮影とほぼ同時に立体映像を確認できるワークフローが組まれていた。ベースで確認した映像を現場側のディスプレイにも戻し、スタッフ全員が同じ立体映像を共有できるようにしていた。
実際に空間再現ディスプレイで撮影中の映像を確認すると、肉眼で見るような奥行きと臨場感があり、従来の2Dモニターでは得られない立体感が得られていた。

リグの左右視差の調整は、立体映像の品質を左右する重要な工程だ。現場では調整用チャートを用い、レンズ交換のたびにセンター合わせが行われていた。ソニーPCLのステレオグラファーやポストプロダクション担当者が常駐し、リアルタイムで視差調整を続けることで、撮影段階から最終品質を見据えた運用が行われていた。

裸眼立体視を可能にする空間再現ディスプレイの技術
今回のプロジェクトの核となる空間再現ディスプレイは、2Dモードと3Dモードを備えたモニターである。2Dモードでは一般的なモニターとして複数人での視聴に対応し、3Dモードではディスプレイ上部の視線認識センサーが視聴者の顔と両目の位置を捉え、左右の目に異なる映像をリアルタイム生成することで、メガネなしの立体視を実現する。

パネル自体は4K解像度だが、左右別映像を扱う構造と表面の特殊光学フィルムにより、表示は「4K相当」となる。右目用・左目用の映像を事前に用意し、それらを合成した信号を一本のHDMIケーブルで送出。ディスプレイ側で映像を分離し、特殊フィルムを通して各目に対応する映像を投影することで立体視が成立する。
左右映像を一本の信号にまとめる処理は、撮影現場のベースステーションで行われる。カメラからの2本の映像信号をそこで統合し、空間再現ディスプレイへ送信する。このプロセスにより、現場でリアルタイムに高精細な立体映像が確認できる。


ソニーはこのディスプレイを家庭用テレビではなく、映像制作現場やポストプロダクションにおける確認用モニター、エンタテインメント施設やショールームでの没入型体験など、プロフェッショナル用途を中心に位置づけている。一方で、Inter BEEやソニーストア銀座での展示を通じて一般ユーザーにも体験の場を提供しており、27インチモデルに加え、将来的な大型モデルの商品化も視野に入れている。今回の制作では27インチを主に用い、プロトタイプの75インチを鑑賞用として試用した。
空間再現ディスプレイが織りなす没入体験の核心
撮影とポストプロダクションを終えた後日、完成した「Laundry」を75インチの空間再現ディスプレイで視聴する機会を得た。人物のサイズが視聴者の体格に近いため、画面内の存在感が強く、現実に近いスケール感で体験できる。


ディスプレイと視聴者との距離、被写体の大きさのバランスが、立体感の気持ちよさを際立たせていた。手前の人物から奥の背景にかけて奥行きが自然につながり、逆光や浅い被写界深度といった3Dでは難しい要素も破綻なく表現されている。
背景の奥行きが豊かでありながら、手前から奥までピントが破綻せず、精緻な描写が没入感を高めていた。この映像品質は、ソニーのハイエンドカメラとディスプレイ技術が組み合わさることで成立していると言える。


ハイエンドカメラによって粒子感や質感が高まり、「映像」であることを意識させない、実物がそこにあるような感覚が生まれていた。一般的な映像で感じるコマ数の粗さや画質の荒さが抑えられた結果、映像の存在感が前に出すぎず、視聴者は空間そのものに意識を向けやすくなっている。
次世代3Dが拓くコンテンツ表現の未来:会田氏が語る「脳で見る」リアリティ
現代のコンテンツは、テレビや映画だけでなく、小説、漫画、ゲームなど多角的な展開が求められている。ソニーの新たな空間コンテンツ撮影技術は、その中でどのような可能性をもたらすのか。「Laundry」の撮影監督・会田正裕氏に話を聞いた。

――コンテンツ制作において多角的な展開が求められる現代において、今回の技術はどのように可能性を広げるとお考えでしょうか?
会田氏:
これまでの3Dは、技術的な制約が多く、破綻させないことに意識が向きすぎて、表現面で妥協せざるを得ない場面が少なくありませんでした。今回は、人間の平均瞳孔間距離に近い約65mmのベース幅で撮影し、「そこにいるように感じる」臨場感と「空気感」を積極的に狙っています。私が長年こだわってきたのは、「目で見る3D」ではなく、脳に直接届く3Dです。これまでタブーとされてきた表現にもあえて踏み込み、体感としてのリアリティを引き出そうとしています。
空間再現ディスプレイがメガネなしで立体視を可能にするのも、まさに脳に直接訴えかける効果です。映像の奥行きだけでなく、脳に深く入り込むような「深度」が加わっています。今回のソリューションで提案したかったのは、空間全体を自由に移動できるような説得力です。まるでその空間の一部を切り取ったかのように体感できるのが面白さです。「想像してください」と伝えたい。画面の外側に広がる世界を想像してもらうための、その一部を展示しているのです。これは単なる3D映像の焼き直しではなく、「脳で見て、リアルな本物の立体感を体感する」という経験をInter BEEで提供することで、コンテンツのあり方が変わるのではないかと考えています。
一つのコンテンツがテレビや映画だけでなく、小説、漫画、ゲームなど多角的に展開する現代において、この技術は未来の映像表現の可能性を広げ、コンテンツ制作に新たな幅をもたらすと感じています。今回の展示は、3D映像に留まらないソリューション提案の一歩なのです。
――今回の空間コンテンツだからこそ従来の3Dとは異なる意識した点、例えば先述のボケ感や、その他にもアドバイスいただいた点について、さらに詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
会田氏:
従来の3Dでは、見る人が視点を選べるようパンフォーカスが一般的でしたが、私たちはあえて「ボケ感」など、より映像的な表現を追求しました。2D映像でも立体感は表現できますが、3Dはレイヤーを分けるだけでなく、物の立体感を直接感じられる点が大きく異なります。私たちが撮影監督として光や影を操り、平面の中に奥行きを表現してきたのは、脳が顔の丸みや奥行きを認識するプロセスに働きかけるためです。今回の3Dは、その脳の働きをさらに能動的に促し、より深い深度と内側に入り込む感覚を増強する効果があると感じています。
ハイエンド機VENICE 2と高精細なディスプレイの組み合わせは、色彩の無理がなく、映像的なクオリティを最大限に引き出します。大画面での没入感や、小画面でのドールハウスのような面白さなど、多様な表現のインパクトが生まれます。もはや欠点と捉える要素はなく、あらゆる可能性が秘められています。久しぶりに3Dに触れ、その表現領域の広さに驚きました。「これならこんなことができる」というアイデアが次々と湧き、ヘッドマウントディスプレイと組み合わせれば、音響も立体化し、振り向けば映像があるような、新たな次元の実写表現も可能になるでしょう。
カメラ技術の進化についても、「これ以上の画質は必要なのか」「8Kをどう使うのか」という意見もありますが、私はまだ秘められた可能性を信じています。右目と左目のために打たれる8Kのきめ細かさは、もはや技術を感じさせず、まるで別次元の映像体験を提供します。これまでの3Dが偏光レンズなどで仕組みを感じさせたのとは対照的です。撮影は非常にシンプルで、小型の機材で簡単に撮れることに驚きました。にもかかわらず、出来上がった映像は見る人を驚かせるでしょう。

――今回の撮影で最も苦労されたところを挙げていただくとしたら、それはどこになりますでしょうか?
会田氏:
実は撮影自体にはほとんど苦労はありませんでした。技術的な対応も早く、ステレオ撮影がこんなに楽だったかと驚くほどシンプルでした。最も不安だったのは、想像していたイメージのものが本当に出来上がるのかという点です。しかし、「なるようにしかならない」と開き直って臨みました。監督としての期待に応えられるかという不安は常にありましたが、撮影が進むにつれて絵を見て安心し、ワクワクしていきました。
特に、敢えてタブーに挑んだ冒険的なカットは、理屈で言えば危険なものでしたが、結果的に多くの方に気に入っていただけました。逆光や手前の暗い部分など、技術的にも表現的にも難しい状況は、見る側にとってエモーショナルに響くものです。人間の目と同じ距離で撮影しているからこそ、レンズに光が入るような状況でも「人間の目だってそうでしょう」と開き直ることができたのです。
――今回の映像をご覧になった方々、特にカメラマンの方々は、「新しい表現」だと感じられることと思います。見る人に勇気を与え、大きな刺激となる映像だと思いました。
会田氏:
「3Dの次」というよりも、むしろ「2台の映像の一部を切り取った」という表現が適切だと考えています。「脳で見たい」「目で見ないで」というイメージで制作を進めると、目の前にパッと世界が広がり、見る人の想像力を掻き立てるような映像が生まれます。実際に視聴者の方々から「おお」という感嘆の声が聞こえた時は、本当に嬉しく感じました。あのディスプレイで見るあのカットは、通常の視聴体験とは一線を画すものでしょう。
これは単なる「3D」という枠に収まらない、もっと多くの可能性を秘めています。例えば、映画の部分的なシーンを本格的なステレオで撮影したり、サイネージへの応用も考えられるでしょう。ブームが来てから慌てて始めるのではなく、もっと積極的にアプローチしていくべきだと感じています。技術者だけでなく、プロデューサーなど企画する側がこの魅力に気づき、「こんな道具があるなら、こうしてああしよう」と想像力を働かせることが重要です。ソニーが想像していないような使い方を、私たちクリエイターから提案していく、そんな盛り上がりがInter BEEで生まれてほしいと願っています。
デバイスは今後も急激に進化するでしょう。ヘッドマウントディスプレイにも非常に興味がありますし、解像度もどんどん上がっていくでしょう。そうすれば、それに合わせたコンテンツが求められますが、必ずしも専用のコンテンツである必要はありません。多様な見方に対応できるツールとして、この技術がコンテンツ開発のハードルを下げ、面白さを増幅させることを期待しています。
会田氏の言葉からは、単なる技術進歩を超えて、視聴者の体験を起点に映像表現を組み立て直そうとする姿勢が見えてくる。空間再現ディスプレイが切り開く「脳で見る」新しいリアリティは、今後の映像制作を変えていく出発点になる。


























