
txt:安藤幸央 構成:編集部
映画タイタニックのデジタルドメイン、創業者スコット・ロスが語る「VFXの過去・現在・未来」

今回のSIGGRAPH 2025で、スペシャルセッションに登場したのは、VFX業界の先駆者スコット・ロス氏であった。
今ではスターウォーズの特殊効果担当として広く知られるILMで「アビス」「ターミネーター2」「ジュラシック・パーク」といったVFXの黄金時代を過ごしてきた。
ロス氏は、1993年にジェームズ・キャメロン、スタン・ウィンストンと共にデジタルドメイン社を設立した人物だ。自伝「Upstart」を出版したばかりのロス氏は、栄光と葛藤、そしてVFX業界の課題を赤裸々に語った。
SIGGRAPHは「技術」ではなく「文化」
スコット・ロス氏が、まず思い出すSIGGRAPHの象徴は、学術論文や最新機材ではなく「パーティー」とのこと。
予算が乏しい中、ベンダーにスポンサーを募り、チケット制で開催。パーティには人気のミュージシャン、ストレイ・キャッツやビリー・アイドルが登場し、その当時のSIGGRAPHはダンスとテキーラにあふれていた。
この「カルチャー(企業文化)」重視の姿勢はロス氏の経営哲学にもつながる。ロスは自らを「何でも屋だが専門家ではない」と評しながらも、仲間を結びつける場をつくることに全力を注いだのだ。

母の教えと「Upstart」
ニューヨーク・クイーンズの移民系下町で育ったロス氏。母親は常に彼に問いかけていた。
「人類を助けたいの?それともお金を稼ぎたいの?」
ロス氏は表向き「人類を助けたい」と答え、心の中で「でもお金も欲しい」とつぶやいたという。
そのロス氏の半生を綴った「Upstar」は、ADHDを自覚する彼が一人で一冊の本を書けるはずもなく、作家ジョアン・レヴィンと共著する形をとった。週3回各2時間のミーティングを繰り返し、断片的な記憶をつなぎ合わせて完成させた書籍なのだ。
「ロックンロール経営」と3本脚のスツール
ロス氏が提唱する仕事への姿勢は「ロックンロール文化」だ。それは、
- 全力で働き、全力で遊ぶ
- 即興的に仲間と響き合う
- 権威に逆らい、楽しむ精神
デジタルドメインでは映画ターミネーターのセリフをもじった「Come with us if you want to live.(死にたくなければついてこい)」をグッズに印刷してチャリティ活動を行い、オフィスには海賊旗を掲げていたそうだ。
この姿勢はデジタルドメイン社の「3本脚のスツール」経営哲学にも影響を与えることになる。脚が1本、2本の椅子は立っていられない。4本あれば椅子は安定して立っていられるが、コストがかかる。3本脚の椅子(スツール)は、ぎりぎり安定して立っていられる脚の数なのだ。
- 1本目の脚:カルチャー(企業文化):経営者は現場と同じ目線に立つべし
- 2本目の脚:クリエイティビティ:失敗を許容し、挑戦をたたえる
- 3本目の脚:財務基盤:利益なき経営は社員も未来も守れない
ロス氏はILM時代、総監督であるジョージ・ルーカスの「設備投資禁止令」を破り、当時高額であったAppleのMacintoshを大量導入し、社員の士気と創造力を蘇らせた。
「現場を信じ、必要な投資を惜しまない」。それがロス氏の流儀なのだ。
VFX業界を蝕む「地獄のビジネスモデル」
ロス氏が最も強く批判したのはVFXの契約構造である。
製作費は常に値切られ、契約は固定価格。追加修正も無償で対応せざるを得ず、スタジオの裁量に振り回される一方で、リスクはすべて映像制作業者が背負う。
例えば映画タイタニックでも「パシフィックカモメではなく北大西洋カモメに差し替えろ」といった監督の一言で膨大な作業が追加されても、追加報酬はゼロ。
当時のプロデューサーの嫌味な言葉は「VFX会社を一つ潰さなければ映画制作の仕事をしているとは言えない」だった。
ロス氏は何度も業界団体設立を試みたが、邪魔をされ頓挫。映画「ライフ・オブ・パイ」のアカデミー賞受賞時の抗議活動も遮られ、せっかくの演説は「ジョーズ」のテーマ曲で強制終了された。
「ハリウッドがいかに我々を軽視しているかの象徴だ」とロス氏は憤る。
(※2013年、映画「ライフ・オブ・パイ」でリズム&ヒューズはアカデミー賞視覚効果部門賞を受賞した。それは同社が倒産した11日後のこと。完璧な仕事をしても収益がVFXに回ってこず、VFX業界の契約構造により会社が潰れてしまうという悲しい事例。
この辺りの事情は「LIFE AFTER PI」というドキュメンタリ映画で公開されている。)
デジタルドメインの創設とキャメロンとの決裂
ILMを追われた42歳のロス氏は、家族を養うために新たな道を模索する。
仕事の依頼電話は鳴らず、唯一の依頼は映像企業「ショースキャン」のCEO職。そこでロス氏は監督ジェームズ・キャメロンと出会い、さらにジュラシック・パークで冷遇されていたスタン・ウィンストンも加わった。
そしてIBMからの1,500万ドル(約22.5億円)の出資を得て、デジタルドメインが誕生する。
ロス氏は創業メンバーとして精鋭を採用し、映画「ホワット・ドリームズ・メイ・カム(邦題:奇跡の輝き)」や、映画「タイタニック」で数多くのアカデミー賞11部門を獲得するまで成長させた。
しかしキャメロン監督との関係は悪化。キャメロン監督は、自分は神だと思っていた。私はそうは思わなかったとロスは振り返る。
最終的に取締役会でキャメロンは会社を辞め、両者の関係は決裂した。
AIと労働の未来
ロスはAIを「火の発見に匹敵する衝撃」と表現し、VFX業界の未来に強い警鐘を鳴らした。AIは若手や経験の浅いメンバーの職を奪い、成長や育成の段階を破壊してしまう。
つまりはAIの出現によって人材を育てることができず、今後中堅人材が枯渇する恐れがあるのだ。
「AIは単なる道具ではない」
AIによって新たな仕事領域(医療、教育、商品マーケティング等)は生まれるだろうが、従来のVFXの仕事量は縮小し続ける。アーティストはAIを学び、理解し、応用先を見つけなければ生き残れないのかもしれない。
音楽と広島への想い
ロス氏にとって真のヒーローは映画監督ではなく音楽家であった。
若き日に音響エンジニアとしてマイルス・デイヴィスやオールマン・ブラザーズのツアーに同行し、ジミ・ヘンドリックスの楽曲制作に参加した経験は、ロス氏が大切にする「即興とコラボレーション」の感覚を育てた。
また、ロス氏の情熱的な企画に「千羽鶴」という広島を描く脚本がある。
核兵器の恐怖を描くことで世界に警鐘を鳴らしたいと願い続けてきた。現在キャメロン監督が同じようなテーマの映画を企画中だが、ロスは「作品が真に人々を動かすなら、誰が監督しても構わない」と語る。
セッションの最後、ロス氏はこう語った。
ロス氏:本当の力は、人に力を与えることだ。権限を分け与えるほど、会社も自分も強くなる。
彼の言葉は、VFX業界だけでなく、あらゆる組織に通じる普遍的な教訓として受け取ることができる。
デジタルドメインの創業者の一人、スコット・ロス氏は2025年現在73歳、この講演は、ハリウッドの構造的問題への告発であると同時に、AI時代を生き抜くための強烈なメッセージでもあった。
ロス氏はロックンロールの反骨精神を大切にし「人を輝かせるリーダーシップ」の重要性を語り続けた。
NVIDIAの勢い:AIが切り拓く映像表現の新時代
NVIDIA「Neural Shaders」「Neural Materials」「AIマテリアル生成」がもたらすインパクト
生成AIの計算環境として膨大で、唯一のシリコンチップを提供する最盛期のNVIDIAから、SIGGRAPH 2025ではグラフィックスの転換点ともいえる新しい研究成果が紹介された。

SIGGRAPHにおいて、NVIDIAは「AIがグラフィックスを変革し、グラフィックスがAIを変革する」というテーマで研究成果の発表が行われた。
映像業界においてNVIDIAのGPUが担ってきた役割は言うまでもなく、今回の発表はシェーダー内部でのAI活用や、複雑な素材のリアルタイム表現、さらにはAIアシスタントによる質感生成といった革新的アプローチが示された。
- Neural Shaders:ニューラルネットワークをシェーダーに組み込み、マテリアルやテクスチャを高圧縮・高精度化
- Neural Materials:従来は不可能だった多層反射素材を、一層の平易な素材並みのスピードでリアルタイム再現
- AIアシスタントによるマテリアル生成:CADモデルにプロンプトと形状情報から即時に質感を適用
Neural Shaders:AIが描く新しい「シェーディング言語」
NVIDIAが「Neural Shaders」と命名した技術は、GPUのシェーダーコード内でニューラルネットワークを直接実行可能にするもの。これにより、従来のアルゴリズムベースでは扱いきれなかった表現がAIによって可能となる。
例えば、テクスチャ圧縮では既存のブロック圧縮に比べて7〜10倍の高圧縮率を実現しつつ、劣化のない高品質描画が可能になる。
加えて、従来は固定的に扱うしかなかった物体表面における光の反射特性や物質の質感表現が、AIの学習済みモデルを通じて柔軟に再構築され、映像制作の作業流れの中で利用することができる。
映像機器業界にとって、これは「表現の自由度」と「処理効率」の両立を意味する。映画制作や放送現場においては、限られたメモリやコンピュータ資源の中でフォトリアルな映像を扱う必要があるが、Neural Shadersによって大規模プロジェクトでも高解像度かつ高速で作業を回すワークフローを実現できる可能性がでてきたのだ。
Neural Materials:多層反射のリアルタイム化

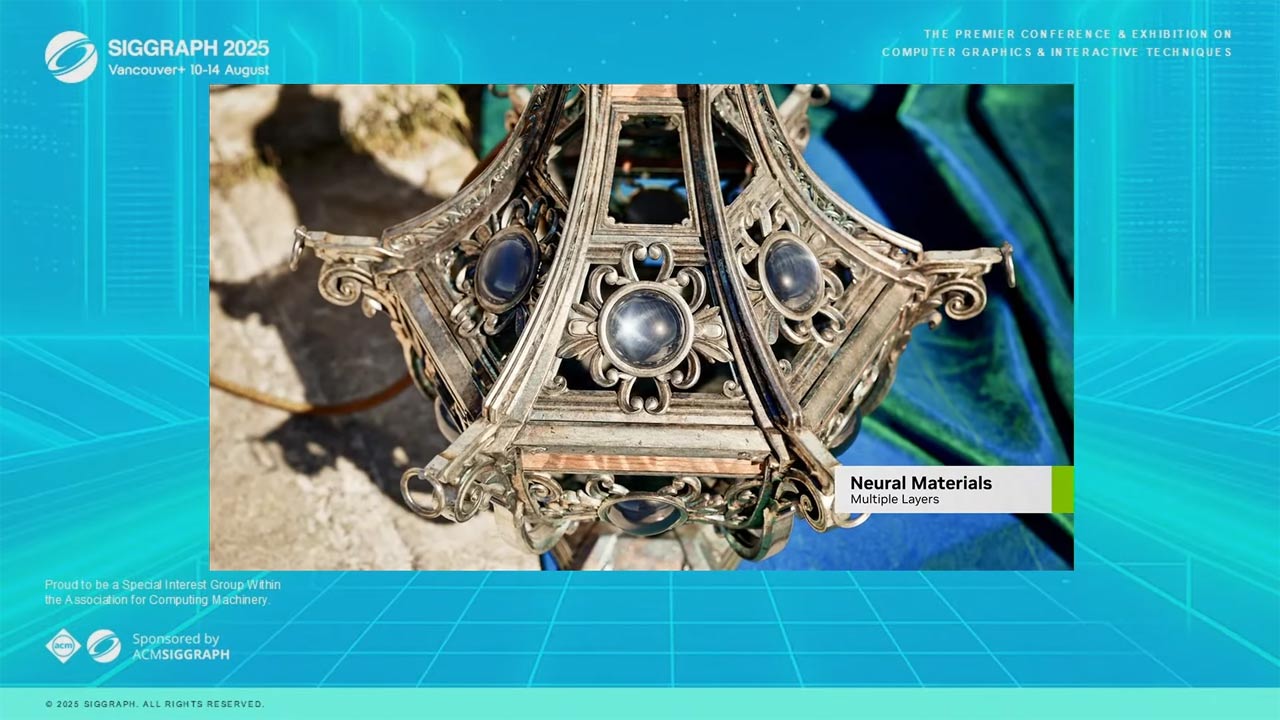
次に紹介された「Neural Materials」は、人間の肌のような複雑な物体の表面における複数層にわたる反射・透過・散乱といった物理的現象をニューラルネットワークによって圧縮表現し、一層しかない単純なマテリアルと同等の計算コストで再現する技術だ。
発表では「スターサファイア」の例が示された。通常であれば1層の20倍以上の計算コストを要する多層構造を、Neural Materialsではリアルタイムに描画可能としている。
映像業界では、金属、ガラス、宝石、樹脂、繊維といった複雑な素材表現が映像のリアリティを決定づける要素である。
これまで高い計算コストゆえに特定用途に限られていた表現が、リアルタイム合成やインタラクティブ映像制作に適用可能となることは、バーチャルプロダクションやライブ配信における質感表現の飛躍的進化を意味する。
AIアシスタントによるマテリアル生成:形状データに瞬時に質感を付与
3つ目の革新は、AIアシスタントによるマテリアル生成だ。形状モデルに対して、形状情報とテキストプロンプトを与えるだけで、即座にリアルな質感を適用できる仕組みが発表された。
この仕組みは、NVIDIAのFoundation Modelをベースに、表面の情報や位置情報を入力とし、AIが「反射率」「粗さ」「テクスチャ」といった情報を出力。さらに、それを3D空間に再投影して質感付きのモデルを生成する。
この技術は映像機器業界にとってのインパクトは計り知れない。例えばバーチャルスタジオで使うその空間に合ったリアルな小道具や背景を形状データから即時生成。
製品CMにおける新製品モデルを物理サンプルなしでリアルに質感再現したりもできる。従来、質感表現には職人的スキルと長時間の作業が必須だった工程が、AIアシスタントによって大幅に自動化されるのだ。
映像機器業界にとっての意味
今回の3つの発表は、いずれも「AIを制作作業のワークフローの中核に組み込む」という点で共通している。
そしてその成果は、映像機器業界に次のような変化をもたらすことが考えられる。ロボティクスや自動運転などへの応用も考えられている。
- 制作速度の飛躍的向上:質感生成の自動化により、プリプロダクションから本番レンダリングまでのリードタイムを短縮
- ハードウェア需要の進化:放送・スタジオ用レンダリング機器の充実が加速
- 新しい表現領域の開拓:これまで時間をかけたレンダリングに限られていた多層マテリアル表現が、ライブ映像やリアルタイム演出に適用可能
- 人材育成のシフト:従来のシェーダーコーディングスキルに加え、AIを活用したマテリアル生成・最適化スキルが新たな必須能力となる
NVIDIAは今回の発表を「Neural ShadingはレンダリングをAIロケットに直結させる」と表現した。これは単なる性能向上にとどまらず、映像制作そのものの概念を再定義する動きでもある。
今後、映像機器業界においては、カメラやディスプレイといった物理的デバイスの進化に加え、こうしたAI駆動型の映像生成技術が競争力の源泉となることが予想される。
AIアルゴリズムがアートを創造できるのか、アーティストと見なされ得るのか
Adobe研究所:Dr. Aaron Hertzmannによる講演「Can Computers Create Art?」

ネットワークを用いた技術による生成アートの隆盛を、歴史上の油絵、写真、従来のコンピュータグラフィクスと並列して考察したもの。
アートはそもそも社会的行為であり、現時点ではAIが「芸術家」として扱われる可能性は極めて低いという立場を示している。
とはいえ、AIは過去の技術革新と同様にアートの制作方法や理解の仕方を変革する力を持っている、という見解も述べられている。講演は論文「Can Computers Create Art?」(2018年)にもとづく発表であった。
「コンピュータはアートを創造できるのか?」
技術的進歩が芸術に与える衝撃と可能性を見据えながら、私たちが抱くこの問いに対し、Adobe研究所のAaron Hertzmann氏は歴史と哲学から丁寧に考察している。
写真やアニメーションの誕生は、当初は伝統的な画家たちに脅威と受け止められた。しかし、結果として新たな表現領域と職業の可能性をもたらし、芸術そのものを豊かにした事例でもある。
Hertzmann氏は、このように技術は芸術を「侵食」するのではなく、「拡張」してきたと主張している。
現在、AIは絵画や映像の自動生成といった形で目覚ましい進化を遂げているが、著作権や創作者としての帰属は、あくまでAIを「扱った人間」にあるという立場をとる。
AIは革新をもたらすツールにすぎず、主体としての人間を置き換えるものではない。
では、将来的にはAIそのものが「作者」として認識される可能性はあるのだろうか?
Hertzmann氏はその可能性を一蹴はしない。
なぜなら、芸術とは意図、文化的文脈、人間同士のコミュニケーションといった要素を含む「社会的行為」であるから。
現在の状況では、コンピュータにはその条件が欠けており、コンピュータのことを芸術を創った「作者」として承認することは難しい。
しかし将来、人々がAIを「社会的主体」として受け入れるようになった場合、AIが作者と認められる可能性も否定できない。その展開には倫理的にも哲学的にも慎重な検討が必要だ。
結論として、極めて微妙バランスを保ちつつ、AIが芸術制作において果たす役割を再定義する機会が求められている。
ツールとしてのAIの進化は歓迎すべきものであり、その創造力は私たちの文化を広げながら進化していくであろう。一方で、「芸術とは何か」「作者とは何か」という問いは、人間中心の文脈に根ざしている限り、「AIにはまだ芸術家の座を譲れない」という認識を今回の講演が浮彫りにしていたのだ。

























