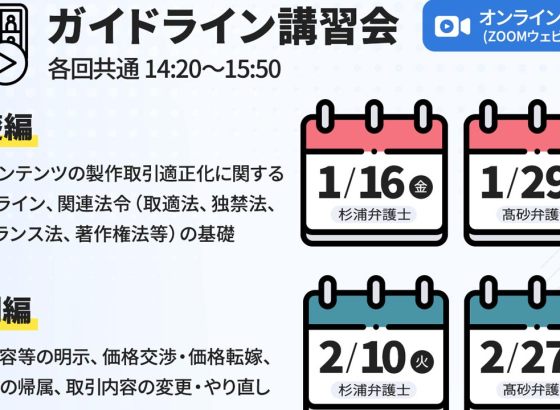Cine Gear 2021がリアルに開催された!
Cine Gear 2021が9月23日から9月26日(展示会は9月24日から9月25日)まで開催した。映画関係者技術であれば参加必須の展示会である。コロナ禍で世界中の展示会はこの2年迷走を続けているが、無事リアルに開催できたことは次のステップへの光明と言えるだろう。

今回、Cine Gear 2021の会場は、L.A.コンベンションセンターでの開催となった。恒例のパラマウントスタジオでの開催も厳密な対策ルールで開催が認められず、事務局は安全面で非常に高い水準にあるL.A.コンベンションセンターを選択した。
出展者と参加者のためのスペースが十分に確保されている。また入場にも厳しいルールが設けられた。ワクチンの接種証明か3日以内のPCR検査の結果が義務付けられために、不参加の関係者も多かったのではと予想される。来場して入場拒否される参加者も少なからずいたようだ。
規模が縮小され、参加企業も少なかったため、当然参加者は多くはなかったが、普段より若い層が目立っていたという。

映画関連の大手企業がほぼ出展してなかったこともあり、小さい規模感であることは否めない。今年は大手企業が軒並み不参加となった。ARRIやPanavision。さらに、キヤノン、ソニー、Panasonicシネマ部門、REDなども今回は出展を見合わせた。

そんな中Carl Zeissなどはブースを設けるなど、小規模ながらもこの状況下中でも積極的なアピールと意気込みがあり、通常開催では不可能だったゆっくりなコミュニケーションが取れたという。
コロナ禍で新商品開発もそこまで進んでいない企業も多いこともあり、新製品が並ぶわけではないが、2021年にWeb上でのみ発表された製品を実際に見ることができるのは醍醐味とも言える。
いつもの開放的で自由な雰囲気とは異なるCine Gearとなったようだが、PRONEWSとしてもCine Gearは、大いに気になるところだ。今回はLA在住の撮影監督である石坂拓郎氏にお話を聞きながらCine Gear 2021を見ていこうと思う。
SISU Cinema Robotics

ロボットアームといえば、Boltなどがお馴染みだが、SISUはさらにユーザーフレンドリーだという。SISUのソフトウェアは優秀で、監督やカメラマンのダイレクトに応えるように、感覚的、直感的にロボットのカメラ位置を設定したり、その間の動きをつけることが可能だ。
コントローラーがゲーム感覚で3D空間のカメラの移動をサポートしてくれる。扱う人の役目に応じて動作方法を選択可能だという。

まだベーターソフトの開発段階だが、点から点の移動を直線的でない円を描いた移動などへの曲線変換も自動的に設定可能と、かなり使い勝手の良いソフトに仕上がっているようだ。年内には完成するとのこと。
石坂氏:これまでもロボットアームは幾度か使用した事はありますが、思ったよりもカメラの配置に手間がかかり、そこからの動きを入力するのにも手間がかかる印象です。それを全て解消してくれるのがSISUだと言えます。ほぼ全ての指摘したロボット系のカメラアームの使用時の欠点をしっかりと考えて修正していました。使い勝手が簡単で直感的であることが、何よりも良かったです。
Breakthrough Filters

フィルター業界に新たに参入してきた新星Breakthrough Filters。スチル業界からシネマにも進出しメーカーだ。
石坂氏:中国からの進出も多くなっているフィルターメーカーの中で、新しいところか?と思っていましたが、、製品品質と彼らの商品詳細に直接触れることができたのは、今年一番の発見だと思いました。
一見同じフィルターに見えますが、NDもCPLもすべてしっかりと可視光線の波長を大切に、色ズレしない作りになっています。これは、社長のGrahamさんが結構こだわっている部分だと感じました。色ズレしないで必要な部分だけを通すという事を大切にしています。

ドロップインフィルターを使用できる様に、ソニー、富士フイルム、RED、キヤノンなど、各社のマウントからPLに変換する間にドロップインフィルターが入るマウントが作られている。各社マウントに対してそれぞれ専用に開発しており、フォーカスの距離に問題が出ないようにセンサーからの距離をしっかりと計測して設計されている。

ドロップインフィルターにより、ドローンなどの撮影はかなり効果のある。またNDとCPLのコンビなども発売されている。さらにBreakthroughのVNDは、今までのVNDと異なり、濃くなった時に色ずれが起こりにくい設計になっている。
これまではVNDとCPLの両⽅を併用して使う事が出来なかったが、Breakthrough FiltersのVNDは、それを可能にしている。そのほかに1ストップCPLなども⼀絞りだけの利点だけでなく、色がクリアに出る事ことでも定評のあるフィルターである。
Lindsey Optics

久々にシッカリとしたディレクターズビューファインダーが出てきた。Vista VisionからS35までをプリズムを変換する事で画の大きさを保つのため、多くのフォーマットに対応可能。他メーカーと違い、重量が軽目に設計されている。
デジタルビューファインダーも現在では多くなっているためそことどう棲み分けるかがキーになる。
Musashi Optical System

武蔵オプティクスは、元FUJINONメンバーが参加しているレンズ会社だ。もうすでに日本のレンタル会社には導入されており、S35mm用のズームが高性能で、価格もこなれている。
石坂氏:売れるシネマレンズだとおもいました。Angenieuxよりもはるかに軽くて、何よりも低価格でした。ズームはメンテが大変ですが、これなら東京で対応可能なので、個人持ち?という夢は広がるかもと思ったレンズでした。

THE LIGHT BRIDGE

展示は屋外でも開催されていた。反射板が多く展示され、表面の加工によりさまざまなソフトからハードに反射光の調整が可能なLightBridgeは、種類もサイズも豊富で、これから需要が伸びそうなメーカーである。
中国メーカーのLEDライトに注目
LEDに関しては、中国メーカの勢いが凄まじく、Aputure、Film Gear International、Lightstarなどの出展が目立っていた。
中国映画もいまや予算が100億円規模の作品も多く撮影されるようになっている。当然機材もそのニーズに合わせてどんどん大規模になっていく。そんな急成長に即座に対応し、良質なものを提供しなければならない競争率の高い市場となっている。中国製LEDは年々クオリティもよくなっている。

さらに、プロダクトの種類の豊富さには目をみはるばかりだ。クオリティに対して低コストと、手の届きやすさも魅力の一つと言える。その中でもLightstarは、LEDの隆盛後、ライトが軽く・小規模になる傾向の中、大型ライトを多くラインナップしている。
石坂氏:中でもLightstarが気になる会社でした。やっと大型LEDが低価格で手に入る世の中になってきたなと。渦巻き型ライトの見た目が好みではないのですが、アウトプットはかなり強く、技術は安定してそうです。カラーメーターを使用してしっかり評価してみたいと思いました。

LEDの出力も十分強くなっているが、やはりメーカーによって色のサチュレーションが得られない物もまだあるのが現状だ。
最近、CRIがあてにならない事がわかってきている人も多いと思いますが、新しい測定方法測がいくつか出てきていて、それらが基準値となってLEDの色が統一されていけば、ユーザーにはメリットになりますからね。
来年CineGear2022は、従来通り、6月2日から5日にかけて開催される。 会場はまだ未定となっているが、ぜひまたパラマントスタジオで開催を願う人は多いだろう。