
txt:小林基己 構成:編集部
運行中の車内を5面LEDスクリーンで再現
今回の特集でバーチャルプロダクションをいくつか取材してきたが、大型LEDスクリーンのスタジオは、まだ映像出しは1面で組んでいるところがほとんどだ。そんな折、前回の東映ツークン研究所で同行したHiguchinsky監督から「正面左右天井までの5面LEDで展開しているスタジオがある」と紹介いただき、取材に伺った。
LEDウォールを活用したソリューションを手掛けるディオライトの大屋さんがシステム構築をしており、イベント/ステージに関わる業務をワンストップで提供しているセカンドステージがLEDスクリーンなどのハードウェアを提供している。そのスタジオは、常設というわけではなく、企画内容毎にLEDの大きさや組み方などを変えることが可能。取材で伺ったときは、テスト撮影用にセカンドステージの長津田の倉庫に正面左右の3面を囲む形でLEDスクリーンが組まれていてる状況であった。
なお、取材の日はパネルが長期メンテナンス中だったので3面であったが、通常撮影では可動タイプの前・後・左・右に加え天井の5面を設置している。


ワンボックス車が入っても余裕のステージで、今回のように車の撮影がほとんどだと聞く。紹介いただいたきっかけとなった作品「THE LIMIT」も車内撮影がメインであった。「THE LIMIT」はHuluオリジナルドラマで、限られたワンシチュエーションで展開する密室劇なのだが、ここでは2話分の撮影が行われ、一つはタクシーの車内が舞台、もう一つは高速バスが舞台の回であった。
実は車の走行シーンを撮るのはかなりハードルが高く、都内では牽引で撮影する許可は下りず、しかもバラエティなどでは出演者に運転してもらうこともあるのだが、セリフを言いながらのドラマでは役者の運転はありえない。
テイクを重ねるごとにもう一度同じ場所まで戻って、途方もなく大変なのが現状である。では、合成にすれば良いかというと、移動している車内の照明を表現するのも難しければ、ポストプロダクション作業でかなりの時間を割かなければならない。
筆者もテレビドラマ「素敵な選TAXI」というドラマの撮影を担当した経験があり、タイトル通りタクシーの車内のシーンが大半を占めている内容であった。2014年の撮影当時は大光量のプロジェクターでスタジオのホリゾントにあらかじめ撮影された走行している背景を投影する方法を提案して採用され、ナイターはそこそこごまかせることができた。しかし、昼間のシーンにいたっては投影だと暗部が浮いてしまい合成感が否めない。それをあえて演出に取り入れたりと後半に行くにしたがって大胆になっていったのだが、今シーズン2を撮るなら、この方法を推薦するだろう。
360°の実写素材をLEDスクリーンに投影
このLEDのシステムもCGでレンダリングされた背景ではなく、360°撮影された動画素材を編集したものを流している。しかも、他のバーチャルプロダクションで標準となっているUnreal EngineではなくUnityを再生エンジンとして採用していた。実写素材を360°張り合わせたドーム状の仮想空間をUnity上に作成しその中心から見える映像をLEDスクリーンに投影している。
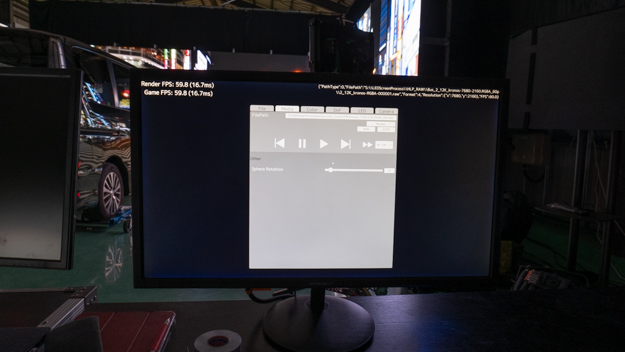
この時はカメラの動きに連動しているというわけではなく、車の位置を基準に3面分、どこを撮影しても成立する背景を意識していた。ただ、元の素材が360°全天周で用意されているわけなので、サイドショットを撮るときは車を横に向けて横に流れる映像を。正面から役者の表情を見せる時は後方を正面スクリーン向けにして後ろに流れていく映像を流すことができる。
3面で構成されていると、スクリーンの繋ぎ目の角の部分が気になるかと思う。そこはサイドピラーなど車体の一部でごまかせる位置を探るなど工夫が行き届いている。

この現場にHiguchinsky監督がVuze XRの「Dual VR Camera」という360°カメラを持ってきていて車内から撮影した素材がある。これがかなり臨場感がある。前述の高速バスのドラマ用の背景素材のため乗用車にしては視点位置が高いが、それさえ調整すれば、かなりリアリティーあるシーンが撮れそうだ。
同じくVuze XRを車の横に置いた映像も残しておいてくれた。車体に映り込む街明かりが美しい。これを合成で表現するとなると作業量が計り知れない。


実はこのLEDスクリーンは2.6mmピッチのものを採用している。LEDパネルを使ったバーチャルスタジオはモアレを避けることからピッチが細かいものが適しているのは確かだ。しかし、これ以上密度が細かくなると、一つひとつの素子が華奢になり設置や解体だけでボロボロと落ちてしまうらしい。それを防止するために表面を樹脂加工するわけだが、それによって反射質な表面になってしまい、照明の反射が気になってくる。
しかも、2.6mmピッチにすることで、コスト削減と軽量化が実現している。軽いことでプロジェクトによって組み替えることも容易になってくるし、1枚単価が安いことで大きなスクリーンにすることができる。大きくできると被写体から距離を置くこともできるのでモアレの危険度も下げることができる。

ディオライトの大屋さんは今までいろいろな映画やドラマの現場経験があるだけあって、理想と現実の絶妙な着地点を探ってくれる。セカンドステージでは50cm×50cmのパネル400枚、H5m×W20mの正に「LEDの壁」を建てることができると聞いた。そうなってくると、我らの憧れ「マンダロリアン」の「Volume」が再現できないものかと思ってしまう。
セカンドステージによると、1mごとに3°、6°、9°の角度をつけることができる金具があり、大屋さんは高さによっては有効角度120°~180°くらいの直径20mの円弧が実現できるという。夢は広がるばかりだ。
ディオライトとセカンドステージのバーチャルプロダクションシステムは、LEDスクリーンの広さを武器に、走行シーンの撮影以外にもいろいろな可能性を感じるシステムだった。
txt:小林基己 構成:編集部
小林基己
MVの撮影監督としてキャリアをスタートし、スピッツ、ウルフルズ、椎名林檎、リップスライム、SEKAI NO OWARI、欅坂46、などを手掛ける。映画「夜のピクニック」「パンドラの匣」他、ドラマ「素敵な選TAXI」他、2017年NHK紅白歌合戦のグランドオープニングの撮影などジャンルを超えて活躍。noteで不定期にコラム掲載。

































