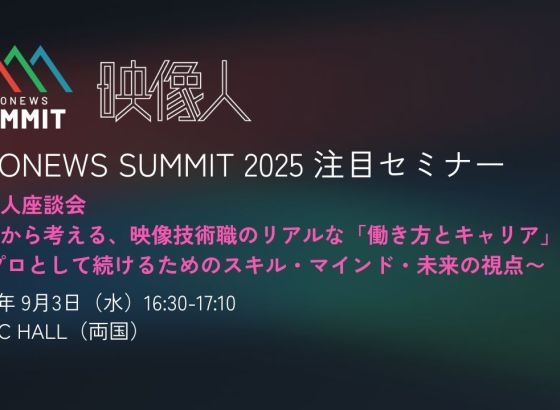ARRIやREDを使う撮影監督が富士フイルム「GFX100 II」を選んだ理由
古屋幸一氏は、多彩な分野で活躍する撮影監督である。映画、ドラマ、Vシネマ、ミュージックビデオはもちろんのこと、インディペンデント映画にも積極的に参加し、その才能を発揮している。撮影担当作として携わった話題の狂気ホラー短編映画「Chime」(黒沢清監督)では、独特のカメラワークが高い評価を得た。また、現在公開中の東かほり監督作品「とりつくしま」や2月公開予定の宇賀那健一監督「ザ・ゲスイドウズ」でも撮影監督を務め、その手腕に注目が集まっている。
そんな古屋氏だが、大学卒業後、九州で広告代理店に就職し、20代を過ごしたのだ。普通に生活していれば、撮影とは無縁の人生を歩んでいた可能性もある。しかしながら、30歳で映画業界に飛び込んだ。
これまでの映像との関わりから、最近の映像作品で使用した富士フイルム「GFX100 II」の感想について話を聞いた。

広告代理店から全く異なる映像の世界へ
――古屋さんは数え切れないほどの撮影監督作品を経験されていますが、この業界に入ろうと思ったきっかけを教えてください。
古屋氏:大学卒業後、8年間九州の広告代理店で事務系の仕事をしていました。当時は長時間労働が当たり前でしたが、給料はほとんど趣味につぎ込み、自宅の暗室やMini DVで写真や映像を楽しんでいました。祖父がカメラや8mmフィルムを趣味にしていて、家族でホームムービーを楽しんだことが、私が映像に興味を持つ原体験でした。
学生時代、映画を観る中でカメラマンの存在を知り、自分でも写真や8mmフィルム、ビデオカメラで撮影を始めました。しかし就職後、30歳を迎えて「本当にやりたいことは何か」と自問した結果、映像の道を志すことを決意しました。
そんな時、日本映画撮影監督協会(JSC)が「撮影助手育成塾」を始めることを知り、1期生として参加。ここで映画の撮影助手としての道が開け、広告代理店を辞めて本格的にこの世界に飛び込みました。
当時はフィルムからデジタルへの移行期で、「RED ONE」や「EOS 5D Mark II」の登場により、低予算でも美しい映像が撮れるようになり、若い世代が次々と映像制作に取り組む時代でした。私もその流れに乗り、映画制作の現場でチャンスを掴むことができたのです。

――古屋さんといえば、国内の映画撮影だけでなく、海外での映画撮影にも積極的に参加しているイメージが強いですが、改めて最近のご活躍のご紹介を御願いします。
古屋氏: 最近は映画やミュージックビデオなど、様々な作品に関わっています。
たとえば、黒崎清監督の「Chime」は45分の作品で、配信プラットフォーム「Roadstead」で配信されるとともに映画館公開もされました。また、東かほり監督の「とりつくしま」という映画にも携わりました。これは彼女の母で小説家の東直子さんの原作を基にした作品です。
若手監督がワークショップ形式で映画制作する「カメラを止めるな」を生んだ「ENBUゼミナール」のシネマプロジェクト作品で、小泉今日子さんも出演されています。現在、大手会社へのリメイク企画を進めています。
さらに、藤田直哉監督の「瞼の転校生」は14歳の中学生3人を主人公に、大衆演劇の役者として転校を繰り返す少年と仲間たちの友情を描いた物語です。
まもなく公開予定の宇賀那健一監督「ザ・ゲスイドウズ」は売れないバンドミュージシャンが地方で生活して、地元の人々と触れ合ううちに売れるバンドマンへと成長していく音楽映画。 低予算感が逆にエモさを演出していて、2024年トロント映画映画祭でグランプリを獲得しています。

現在進行中の映画プロジェクトとしては、ジョージアで35mmフィルムで撮影する映画や、香港人のベテラン映画監督がハリウッドスターを起用して日本文学作品を映画化する作品、海外の監督が日本で撮るドキュメンタリー作品が数本、僕が敬愛する60年代、70年代のサブカルチャー文化を追ったドキュメンタリーなどがあります。
ミュージックビデオでは、乃木坂46の「Actually…」や曽我部恵一さんの「まる。」、MOROHAのアフロさんの新ユニット天々高々の撮影も担当しました。一つひとつの出会いが新たな仕事に繋がり、広がっていくことを実感しています。

大型センサーと映像制作への可能性に惹かれ富士フイルム「GFX100 II」を使用
――シネマカメラとして評価の高いREDを所有されながら、映画祭「MOOSIC LAB」のオープニングムービー撮影では、中判ミラーレスカメラのGFX100 IIを使用されたとのこと。興味を持たれた理由をぜひお聞かせください。
古屋氏: 富士フイルムのカメラはフィルム時代から愛用しており、事務所にはETERNAの缶もあります。過去にはX-T2やX-Pro2を所有しており、その素晴らしさを実感していました。実際に作品で動画を使用したこともあり、富士フイルムはずっと気になる存在でした。

ただ、富士フイルムの色味が少し強いと感じることがあり、好きだからこそ、その映像の個性から一時は距離を置いていました。しかし、GFX100 IIのセンサーサイズを見たとき、その大きさに驚かされました。私はこれまでREDのMONSTROなどフルサイズカメラも使用してきましたが、センサーサイズの大きさには最初それほど魅力を感じていませんでした。
35mmフィルム映画のスーパー35サイズに近いAPS-Cの方が、レンズの焦点距離やボケ感覚を馴染みのある形で表現できると考えたからです。今でもスーパー35が持つ標準性に魅力を感じている部分があります。
フルサイズについては、Amazon Primeのモダンラブ東京のシリーズの一話、黒沢清監督「彼を信じていた十三日間」でカメラがフルサイズセンサーのALEXA LF指定だったことがあり、使用したところ、適切な焦点距離のレンズを使えばフルサイズでも表現の幅が広がり、フルサイズの良さを感じたのです。そこでREDのフルサイズカメラ、MONSTROを使い始め、その良さに惹かれ、定番化しました。そのような流れの中で、さらに大きな33×44というセンサーサイズを搭載したGFX100 IIが昨年発売されました。645フォーマットほど大きくはありませんが、それでも非常に大きなセンサーを持つカメラとして惹かれました。
もちろん富士フイルムの中判カメラとしても気になり、GFX100 IIの告知を見て、映像制作にも活用できそうと思いました。観世能楽堂で行われたGFX100 II動画撮影体験会のイベントに招待いただき、GFX100 IIに触れたところ、やはり素晴らしいと感じました。しかし、そのときは触れただけで終わってしまい、しばらく様子を見ていました。
ちょうど去年の秋頃に、街で撮影する小規模な作品をいくつか手がけることになり、このプロジェクトでGFX100 IIを使うこととしました。

――普段からREDやARRIのシネマカメラを常用されている古屋さんにとって、GFX100 IIはどのように感じられましたか?
古屋氏: やはりセンサーが大きい分、解像感が非常に優れていると感じました。まるで異次元のような解像感です。画素数は1億画素ですが、肉眼で見ても、驚くほどの高画質です。
今回のプロジェクトでは、富士フイルム純正の55mm単焦点レンズとズームレンズとの組み合わせで使用しました。GFXを初めて使用したのは、MOOSIC LABという映画祭のオープニング映像とメインビジュアルの撮影です。最初はスチル撮影から始まりました。
私は写真からキャリアをスタートしたこともあり、写真の仕事にも関心がありましたが、なかなか機会がありませんでした。ただ、「とりつくしま」の東かほり監督が、写真と動画の両方を担当してみませんか、と声をかけてくださったのです。東監督のおかげで、写真撮影の機会を得ることができました。
これまでスチル撮影の場合は、専任のカメラマンが担当することが多く、両方を依頼されることも稀でした。CM撮影のように、写真と動画の両方を担当するのは、現場の規模や進行の都合上、大変なことが多いです。動画撮影後、次の準備をしなければならない中で、スチル撮影も行うのは、テンポが合わず、両立が難しいと感じていました。
そのような理由から、これまで写真と動画の両方を担当することはありませんでした。しかし、今回は小規模なインディペンデント作品で、自分たちが作りたいものを作ることができたので、両方を担当することができました。
GFXは、1回目のシャッターから素晴らしい写りでした。GFXの映像をHDMIでモニターに出力したところ、スタッフの反応も上々でした。1枚目のシャッターを切った瞬間から、手応えを感じました。
モデル:今森茉耶
小型なのに大型イメージセンサーを搭載し、気軽に持ち出せる
古屋氏:また、このカメラの良さは、やっぱり小型であることですね。小型なのにすごく大きなセンサーを搭載していて、気軽に持ち出せるというのが最大のメリットだと思います。
MOOSIC LABは自主制作なので、基本的に僕一人で撮影します。助手もいないので、街中を動き回って、深夜遅くまで撮影することもありました。普段であれば、REDやARRI AMIRAなどを持っていくのですが、今回はどれも違うと感じたんです。
それで、今回はGFXを使ってみようと思いました。GFXを使えば、自分の中でも新たな発見があるんじゃないかと。というのも、MOOSIC LABは普通の仕事とは違うので、何かしら新しい発見があればいいなと思っていたんです。
カメラって、画質はもちろん大事だけど、それ以上に撮る楽しさや、テンションが上がるかどうかが重要だと思います。楽器と一緒で、「このギターが好きだから」みたいに、愛着を持てるかどうかが大切ですね。
GFXを使うと、新しいことにチャレンジする気持ちになれる。僕にとって、カメラは単なる道具じゃなくて、創造性を刺激してくれるという点でも優れていると思いました。

演出:東かほり
モデル:今森茉耶
――古屋さんはフィルム撮影の機会も定期的にあると聞いていますが、その経験からしてGFXのフィルムシミュレーション機能はどのように感じましたか?
古屋氏: フィルムシミュレーションは「クラシッククローム」と「ETERNA」をよく使っています。やっぱり映画らしい柔らかさがありながら、肌の発色がいい感じでとても使いやすいですね。ETERNAの時代は撮影助手で、アシスタントとして参加した作品にリリー・フランキーさん著者で、松岡錠司監督の作品「東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜 」という映画で使用しました。そんなETERNAがフィルムシミュレーションとして使えるというのは、本当にすごいことですよね。






今後はPLマウントレンズと組み合わせた本格的な撮影にも
――最後に、GFX100 IIは、今後どのような活用が考えられますか?古屋さんの今後の展望をお聞かせください。
古屋氏: やっぱり、このカメラの一番の魅力は、小型なのに大きなセンサーを搭載していて、気軽に持ち出せるところですね。画質はもちろん、F-Logで撮影できるのも素晴らしい。今回は普段使いで、写真や動画を気軽に撮影してみました。
次は、しっかりとリグを組んで、三脚に固定して撮影したいですね。PLマウントレンズを使って、本格的な撮影に挑戦したい。その時は、カメラ内部ではなく、外部レコーダーを使ってRAWで記録したいと考えています。
今後登場する富士フイルムのシネマカメラ「GFX ETERNA」は、フィルムシミュレーションに加えてイメージセンサーの読み出し速度向上も期待です。実現できれば様々な現場から間違いなく注目されるシネマカメラになると思います。