
悦楽とは何か
前回まで「リフレーム・異化」「帰属・回帰」「描望」という意味体験タイプを深堀りしてきた。この3つは意味体験タイプの中でもかなり基礎的かつ大カテゴリーなので、これから触れたい意味体験タイプはまだ残っているものの、その多くは上記3つの意味体験タイプと接地している場合が多い。そんな中で、今回は少し筆休みのような、やや閑話休題的な回としてみたい。
前回Vol.16にて、意味体験タイプのマップを示した。これは以前から触れてきた通り、TVCMがもたらす「気分」を大きく分類して可視化したものだ(詳細はVol.03、Vol.04などでも述べてきた)。
今回は、この意味体験タイプのマップを把握しておくことでの効能について、触れてみたいと思う。まずは章タイトルの「悦楽とは何か」というところから始め、そこから展開しつつ解題してみたい。
「悦楽」という概念を説いた中心人物は、フランスの記号学者ロラン・バルトだ。彼はテクストや映像の記号論的解釈を通じて、そこから生まれ得る気分(ないし楽しみ方)を「快楽」(仏語:plaisir)と「悦楽」(仏語:jouissance)という別の次元に分けた。
普段、私たちに提供される(あるいは制作者なら、人々に提供する)ストーリーや表現の多くは、(そのメディアが書物であれ映像であれ)人々にこのような気分で受容されるだろう、という着地=気分の想定を持っている。その多くは、提供側=コンテンツ側があらかじめ設定しているものである。
ディズニーの「ビッグサンダー・マウンテン」ならだいたいみんなこう感じるし、それについてのイメージもそんなに変わらない。椎名林檎の「自由へ道連れ」ならこんな感じ、「課長 島耕作」ならこんな感じ。みんな大体ストーリーをそのまま追って、ストーリーに運ばれるままにエンディングに達し、そこである程度予定通りの読後感を得ていく。
広げていえば諸々の「デザイン」(パッケージデザイン、店舗デザイン、コミュニケーションデザイン、都市デザインetc)もすべてこうした予定調和志向にある、と捉えることも可能だろう。こうした「ある程度想定通り」の消費による楽しみが、バルトのいう「快楽」と捉えて概ね差し支えないだろう。
バルトに沿っていえば、「快楽」は楽しみ方の初級編であり、ヨチヨチの段階である。でも見てきた通り、世界はこの予定調和的な「快楽」に溢れている。想定→提供→消費&楽しみ=快楽(想定通り)というプロセスだ。
バルトのいう「悦楽」はこれとは違う。与えられ消費することでの「快楽」の次元に留まらず、そこから自分なりに別のポイントを発見して勝手に楽しむ、これが「悦楽」だ。もはや作者や提供側の意図は無視され遺棄される。
バルトは「読者をテクストの消費者ではなく、生産者にすること(=作者の死)」を唱えた。こうした、読者や消費者側が、制作側以上に力を持つ関係によるコンテンツ論を一般に「受容理論」と呼ぶ。バルトのこうした主張は、それまでの文学批評の形を大きく転回させた。彼がテクスト論の先達と呼ばれる所以である(ちなみに「テクスト」を「コンテンツ」と言い換えても、現在の文脈でいえば問題ないだろう。当然広義のコンテンツ=環境や社会現象もここには含まれる。つまり知覚・解読可能な対象<のすべて>という意味合いでよかろうと思う)。

画像出典:みすず書房
バルトの著作「テクストの快楽」は散文的で難解と言われることもあるが、バルトが「快楽」と「悦楽」について比較的に触れている部分を抽出し、いくつか以下に示しておく。
快楽のテクスト。それは、満足させ、充実させ、快感を与えるもの。文化から生れ、それと縁を切らず、読書という快適な実践に結びついているもの。
悦楽のテクスト。それは、忘我の状態にいたらしめるもの、落胆させるもの(恐らく、退屈になるまでに)、読者の、歴史的、文化的、心理的土台、読者の趣味、価値、追憶の凝着を揺るがすもの、読者と言語活動との関係を危機に陥れるもの。(「テクストの快楽」P26)
(筆者注:ラインマーカー部分には、引用元では傍点が付記されている。すなわちここでの「快適」については疑ってかかれよ?という含意である)
前半の、快楽のテクストについての部分は、
快楽のテクスト→「普通のコンテンツの楽しみ方」
文化→「社会的主観(みんなが諸々の対象を大体共通してそう感じるような気分の総体)」
読書→「コンテンツ消費」
とそれぞれ代入して読み替えて構わないだろう。前半は「一般的な感覚で消費してフツーに満足するのが快楽」となり、同様に後半は「一般的な感覚が壊れちゃいそうな状態において楽しむのが悦楽」という風に読める。あまり通俗的な解釈をすると研究者から怒られそうだが、意図を汲めば概ね間違っていないだろう。続いてこんな一節もある。
悦楽の非社会的性格。それは社会性の突然の喪失だ。しかし、だからといって、主体(主観性)、個人、孤独の方に再び落ち込むことは決してない。すべてが失われるのだ。完全に。隠密性の極致、映画館の闇。(「テクストの快楽」P74)
悦楽の次元にたどりつくことで社会性を失っても、それに起因するネガティブなヤバさは別にない、というのも密やかに社会と切れるため、それに気づくものすらいないしね、というような意味だろう。
悦楽のテクスト。粉々にされた快楽。粉々にされた言語。粉々にされた文化。それは想像し得るあらゆる目的性を―――快楽の目的性さえも(悦楽は必ずしも快楽を伴わないから、悦楽は一見退屈でさえある)―――持たないという点で、倒錯的である。(中略)中途半端な倒錯は、たちまち、威信、広告、競争、演説、パレード、等々、低次の目的性の作用であふれてしまう。(「テクストの快楽」P97-98)
(筆者注:ラインマーカー部分には、引用元では傍点が付記されている。「悦楽のテクスト」についてだぞ、間違えるなよ!という意味合いだと思われる)
これも同様だ。コンテンツを制作提供する側の目指す楽しみ方や気分を完無視して勝手に楽しむのが悦楽。ただ勝手に楽しむ度合いがヌルいと、すかさず「快楽」側(仕掛ける側の設定)に攻めこまれるぞ、というようなことだろう。
名著「暇と退屈の倫理学」の中で、哲学者の國分功一郎も悦楽について語っている。國分の場合は悦楽という語は用いていないが、その主張は内容的にはほぼ重なる。本中での切り口は「退屈」なのだが、ここに3つの形式があるという。
第一形式は例えば仕事などのルーチン・ミッションに身を投じて退屈をしのぐこと、第二形式はそのルーチンに退屈さを感じるので色々な気晴らしを巡るが、でも結局退屈であること(現代ほとんどの人はこの状態にある)。そして第三形式は「(ハイデガー的)決断」をして今のルーチンから抜け出すこと、なのだが、しかしこれは(再び新たな)ルーチン・ミッションに身を投じることに繋がるため、結局第一形式と同じになるという。
ルーチンなミッションに身を投じて過ごす中では(=第一形式・第三形式)、雑音をできるだけ抑え、妙な潜在性や可能性に自らを開いたりしない。さながら「忙しいとは心を亡くすこと」である。そんなルーチンの間に訪れる第二形式では、日々の抑圧を浄化・解放するべく、レジャーをしたりといった気晴らしをする。けれどこうした時間軸の短い「気晴らし」は概ね、産業側により与えられるサービスにより気晴らしを「消費」することだ。これは前回Vol.16においても触れた通りだ。
単なる消費には「快楽」はあるが「悦楽」は生まれない。國分はここで「与えられた快楽に満足せず、それを否定し、ひたすら進歩を目指して前進していく姿勢こそが人間である」というコジェーヴの言葉を引用して、快楽の次元で満足することを「動物的」であると論じている。
じゃあ悦楽の次元――これが三つの形式を跨いで「退屈」から脱するただ一つの方法だ――はどうかを國分の言に沿って言うと、それは「楽しむ」ことであり、それについては結論の最後の最後(あとがきの直前)に、以下のように短く述べられている。
食べることが大好きでそれを楽しんでいる人間は、次第に食べ物について思考をするようになる。美味しいものが何でできていて、どうすれば美味しくできるのかを考えるようになる。映画が好きでいつも映画を見ている人間は、次第に映画について思考するようになる。これはいったい誰が作った映画なのか、なぜこんなにすばらしいのかを考えるようになる(後略)。(「暇と退屈の倫理学」P353)
生活環境や世界全体をコンテンツと捉え、それらを自分なりの興味・好みからリフレームし、悦楽の態度へ入ることはもちろん、無理がないやり方だろう。ただ食い足りないといえば食い足りない。折角であればここに、もう少し方法論的なことが加わってもよいだろう。というわけで短いが本論に入る。
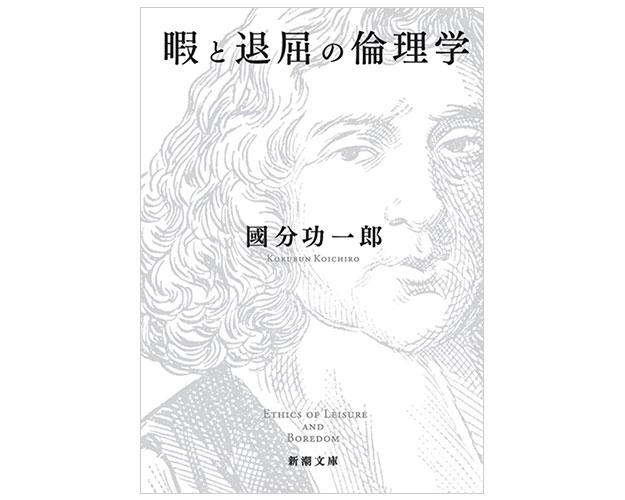
(画像出典:Amazon)
悦楽へのアプローチ
前述の描望の例の通り、私たちが「ちょっとした息抜きをしたい」と望むとき、それを叶えるようなさまざまなサービスや商品は産業側によって数多く用意されてきた。描望のみならず、最近では「ネット化・グローバル化する社会における不安」に対して「自己啓発的な言説」がサービスや商品になっている状況を、哲学者の千葉雅也が見事に抉っている。

(画像出典:Amazon)
我ながらしつこいが、「与えられたもの(提供コンテンツ)をそのまま享受し、用意した側の想定通りの気分に概ね着地」して、しかも満足(それがどの意味体験=インサイトタイプでも構わない)するなら、それは先述の「快楽」である。これに対して「悦楽」の段階は「それをそのまま享受しない」「想定通りの気分にならない」あるいは「もっと●●なものはないのか、と自分で探求し始める」ようなことである。
しかしそのためにはどうすればいいのか?となると「生きがいをみつけろ」「勝手に楽しめる自分になれ」くらいしかない。残念ながらそれ以上のアドバイスは難しいだろう。
とはいえ、本稿に即せばここに2つのアプローチがあるように見える。この2つをさしあたり「制作的可能性」と「受容的可能性(着地する気分の可能性)」としておこう。
「制作的可能性」は上述に沿えば「もっと●●なものはないのか、と自分で探求し始める」という、どちらかといえば能動的なものだ。「与えられたものに納得」せず、その入口では「ああ、こうした方がいいのに」という思索が働く。最終的に自作をしたりする方向性で、制作的可能性すなわち自分で悦楽ポイントを作ろうとすることに近い。
一方で「受容的可能性」は、用意した側の想定通りの気分に着地しない、ということである。
多くの人々が特定の対象に対して、社会的主観を共にしている場合(「健康っていいなあ」とか、「英語喋れるっていいなあ」とか)その好き嫌いに関わらず「ああそういうことを言いたいのね」ということはわかってしまう。
でもはなから「コンテンツが言いたい、そういうこと」を受け取らず(受け取れず)、あえて別方向の気分へ自ら着地させる、ということだ。高度な感じもするが、必ずしもそうではなく、むしろ日常的に試行できることである。そもそも何なんだろうこれは?とリフレームしてみることに近い(決してネガになることではない)。
筆者としては「受容的可能性」から「制作的可能性」が開かれていく、という順番がイメージしやすかったりする。ただここは人それぞれであろう。この部分は最後に再度触れる。
「制作的可能性」と「受容的可能性」はどちらも「それをそのまま享受しない」という意味では結果的に同じだし、最終的には混交していくものでもあるだろう。とはいえ以下考察のために一旦分類し、まず、制作的可能性について見ていくことにしよう。
制作的可能性――制作の潜在性
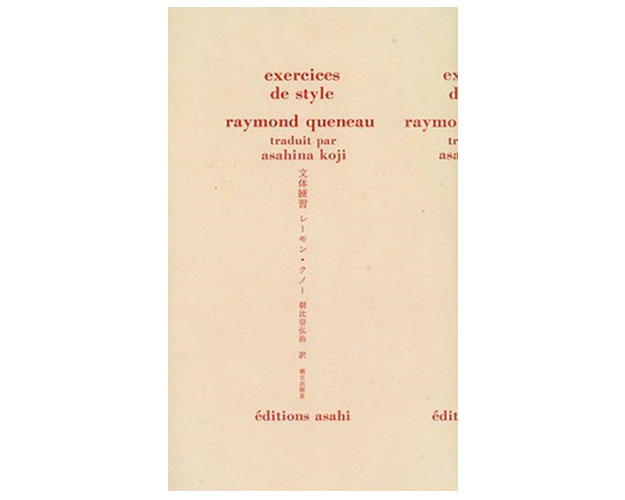
(画像出典:Amazon)
映画ファンであればレーモン・クノーは有名な「地下鉄のザジ」の監督として記憶に残っていることだろう。のみならず彼は「ウリポ」という文芸活動のグループの中心人物であった。それはどんなミッションをもったグループだったのだろうか。
「ウリポ」はクノーを中心に形成されたグループで、"潜在文学工房"の意味を持つ。文学の様式性と数理性を徹底的に追求しようというもので、言葉を因数分解するどころか、微分も積分も射影もしてしまって、そのあげくに「言葉遊びを通した文学の方程式」をつくってしまおうという変な実験だった。 (松岡正剛の千夜千冊 第138夜 レーモン・クノー「文体練習」)
「文体練習」はそんなクノーによる、たったひとつの些細な出来事を、99通りにおよぶ書き換えによって構成した書である。用いられる文体には「荘重体」「俗悪体」「罵倒体」などがあり、方法論としては擬音で表現したものや、視覚だけ、触覚だけに絞ったものなどあり、また植物学、医学のような記述、さらには確率論や集合論的な記述もある。描写もリアルタイムでの記述から回想、夢の中、反復などさまざまなものがある。
制作における編集的な試みの多様性が、こうした具体例が示されることで開かれていくという意味で、「文体練習」は創作のための壮大な参考資料だ。書き手が取り得るさまざまなパラメーターの置換が示され、なにげない文章に対する無限の制作的潜在性を体感することができる。
面白いことに、というか当然ではあるが、こうしたさまざまな文体によって多様な気分が惹起させられる。クノーはおそらく、受容=気分タイプについてもある程度の分類モデルをもっていたのではないか、と筆者は考えている。「文体練習」に、さらに気分の分類がついていれば「さらに実践として使えるもの」になっていたのではないか、とも思えてならない。
そして、これもまた当然だが、映像表現においても「映像での『文体練習』」が可能なはずだ。筆者はTVCMの解析をする中で、比較的詳細に映像の方法論を仕分けた経験から特にそう感じる。
方法論を全体像として見ようと意識していくと、ひとつひとつのTVCMに対して「もっとこうあり得た」という潜在性が当然つきまとう。一方でこの「もっとこうあり得た」と感じる、その大前提には、「それでどういう気分になるか」というパラメーターをどうしても並行、いや先行させざるを得ない。特にTVCMの場合は「快楽」提供側が、どのような受容=気分の着地点を設定しているのか、がすべての起点にあるからだ(多くの場合、制作側にとってもこのことは暗黙的なのだが)。
受容的可能性――受容の潜在性
「文体練習」のような制作的方法論をもってして、ではどうやって悦楽の次元に辿り着けるのか。誰もが辿ることであろうが、人がやっている方法技法を「面白い、やってみたい」と感じるのと、自分でやりこんでみて「これは面白い」と実感することはかなり違う。「文体練習」を読んだところでいきなり悦楽の次元に跳べるわけではない。一方で、自分自身が面白いとノメリこめる方向性と、関心のある方法論が一致すればこんな至福はない。
でも方法技法以前に、何らかの「手始め」が要るだろう。例えばDX関連やM&A関連によくある「レバレッジタイプ」のTVCMに対して「これもっと自由・解放方向にできないのかな」とか、鉄道電気などインフラ関連によくある「帰属回帰タイプ」のTVCMに対して「これもっと自由・解放方向にできないのかな」という意識(というかほとんど無意識)がわくとする。受容の潜在性とは例えばそういうことでもある。そういう瞬間に注目しまくることが大切だろう――自分はまたぞろ「自由・解放」方向に曲げたがってモヤモヤしてるんだな、そういうことか、と。これはまさに「メタ認知」といえるだろう。
多くのことについて「自由・解放(み)」を求めていて、そのための方法論をいくつも持ち始めることができてくれば、そこに自ずから悦楽の次元が始まってくる。しかも、「自由・解放」に変形する方法論にも色々あることがわかってきて、気分としての「自由・解放」の中にも実は細かくいくつものカテゴリーが見えてくる。そうなってくれば「受容」と「制作」は分かちがたいものとして結合してくるのだと思う。
つまり、どのような受容(=気分)を自分は志向しているのか、という状態をメタ認知することが先で、そこからあり得るべき方法論が紡がれていく、というコースが多くの場合起きていることだろうと思う(もちろん方法論先行、というのもあるのだろうけれど)。
とはいえ、受容の仕方すなわち気分のタイプにも様々なものがある。私淑する気分のタイプも当然いくつかあるし、ひとつに絞り切れない。まさに受容の潜在性、すなわち多様性だ。だから結局は気分のタイプについての大きな見取り図(目は粗いが全体感が掴みやすいもの)があったほうがメタ認知がしやすく、制作の方法論もそこに紐づけやすいだろう。自分の悦楽次元への入り口として、ひとつ重要な海図となるはずだ。
ところで、ここのところ「背徳グルメ」というワードが流行している。これは料理のジャンルでも価格でもなく「背徳的」という、惹起される気分形容によってマーケットができた良い例でありそこには「悦楽」が全面化している。インサイトタイプでいえば描望の中の「浄化」の変形バージョンといえそうだ。

(写真出典:FoodClip)
先述のとおり、提供側やマーケットが用意した意味体験を無視して、自分なりの意味体験によって楽しむことが「悦楽」の次元だったはずだ。その次元をマーケットが先取りし始めるのはパラドックスでもあるが、料理のジャンルでも価格でもない「背徳グルメ」は「背徳スポーツ」や「背徳カラオケ」にさえ転化してもよいという意味で、色々な潜在性を開いていく。そういう意味では「お、これは面白い」と感じる気分についてのメタ認知も、受容の潜在性を開くことに貢献するだろう。
一方ですぐこんなことも考えてしまう―――「背徳グルメ」を宣伝するTVCMを考えると、それって大体やり口が見えてしまわないか?と。それを帰属・回帰感や自由・解放感で語る方向感は何かないのか、など。さらにいえば「背徳グルメ」の前後にどのような気分があれば最も効力を発揮するのか、など…。潜在性への思いめぐらせは意外とタフだが、日常所作にすれば強い。
悦楽の注射――意識をメディアに先行させる
悦楽の意味に始まり、制作の潜在性、受容=気分の潜在性ということについて見てきた。日々の生活の中でも、多くの「悦楽の注射」を打つことは可能だ。そのために、多くのモノコトに囲まれた私たちにとって手っ取り早いのは「今・ココ・意味通り」に見えることを「今でもココでもなく、全く違う意味でもありえる」ような潜在性へと開くことで、その瞬間をメタ認知することだ。
しかし、最初からガイドもなしに「開く」ことは難しい(あと意識的にやるのも大抵ダメだ)。受容の潜在性が開いた瞬間=注射の瞬間を大事にする、そこから制作の潜在性へ向かう、という行路が、特に筆者のような凡人にとってはいちばん無理がないように思う。ただ単に制作の可能性を方法論的・技法的に掘っていってもいいけれど、バルトのこの言葉に戻ってみれば、
悦楽のテクスト。粉々にされた快楽。粉々にされた言語。粉々にされた文化。それは想像し得るあらゆる目的性を―――快楽の目的性さえも(悦楽は必ずしも快楽を伴わないから、悦楽は一見退屈でさえある)―――持たないという点で、倒錯的である。(中略)中途半端な倒錯は、たちまち、威信、広告、競争、演説、パレード、等々、低次の目的性の作用であふれてしまう。(「テクストの快楽」P97-98)
それは単なる手癖の方法論―――世に多く出回るシナリオ論などにあるような、悦楽ではなく快楽を成就するためのマニュアル・テクニックに堕ちてしまうこともあるだろう。方法的な手癖で「予定調和な快楽」だけを提供・受容するサイクルは「悦楽」の次元ではない。こうした既存メディア的なゲームに「意識において先行すること」が、私たちにとって(制作においても受容においても)まず最も重要な務めなのではないだろうか。
そのためにも、意味体験タイプのマップをざっくり把握しておくことで、今何に退屈していて、どういう気分を求めているのか。あるいは注射がおきたとして、どういう誘導に対して自分がどの方向へ着地を変えたのか、こうしたことを自然にメタ認知できるようになっておくことは、何よりの基礎になるだろう(実はいつ打たれるのかわからない)。悦楽の注射に注目することを、筆者もまた、もっともっと日常の所作にしていきたいと思う。
WRITER PROFILE


























