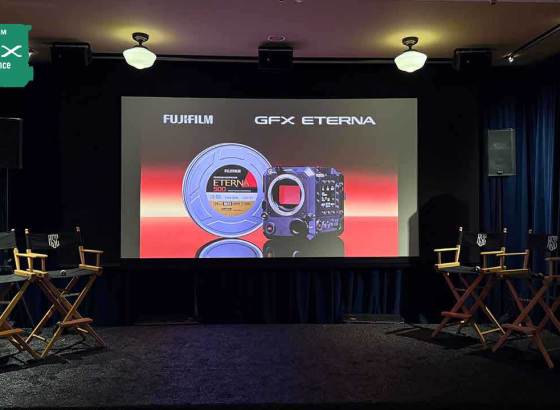富士フイルムから新しく発表された1億画素中判デジタルカメラ「GFX100 II」の実機をお借りしてテストさせていただくことになりました。TFCプラスのシネマトグラファー湯越慶太です。
今回、「写真機」ではなく「動画機」としてGFX100 IIはどうなのか?という観点でレビューをしてみたいと思います。GFX100 IIは先代機GFX100で可能となった4K動画撮影機能に加え、8K動画の記録が可能になり、ProRes 422 HQでの収録にも対応というのが動画面での大きな進化といえるのではないでしょうか。今回はその全てを網羅するというよりは、個人的に気になるポイントを重点的に探るようなレビューにしたいと思っています。
GFX100 II=「ハンディ大型映像」?
動画のフォーマットにおいて、多くの人が気にするポイントの一つがセンサーの大きさではないでしょうか。35mmフルフレームのセンサーで動画が撮影できるようになった時、多くのシネマトグラファーが狂喜して飛びつきましたが、センサーサイズが大きくなることで動画の表現力が飛躍的に高まるという共通認識があったからだと思います。
フィルム写真の時代であれば、35mmフォーマットは「入門サイズ」で、上を見れば645、6×6、6×7、さらに4×5や8×10と、フィルムの面積が増えていく世界が遥かにそびえていました。フィルムの場合、単純に面積を増やすことが高画質化につながりますから、より高画質を求めるのであればフィルムフォーマットは自然と大きくならざるを得ませんでした。
映像もまた然りで、家庭用の8mm、TVドラマは16mm、劇映画やCMなら35mmフィルムを縦送りにした35mmフォーマットまでは比較的よく見る規格ですが、ここまででも写真基準だといわゆる「ハーフサイズ」。35mmを横送りにした「ビスタビジョン」なんて変わり種でやっとスチルの35mmと同じ撮像面積になります。
ではこの上の世界がどうなっているかというと、35mmフィルムの2倍の幅を持った「70mmフィルム」を使った70mm映画というものがあります。写真でいうところの中判とほぼ同じフィルム幅です。歴史的なものなら「2001年宇宙の旅」「アラビアのロレンス」といった往年の大作映画が70mmのフィルムを使って撮影されており、フィルム面積の広さに由来する高画質は現代でも十分通用するものです。
70年代には「IMAX」という、70mmフィルムを縦ではなく横に送ることでさらに大面積、高画質な映像を撮影できるシステムが開発されました。元々はナイアガラの滝とかアフリカの大自然をじっくり撮影するようなカメラだったIMAXを映画に持ち出して、あろうことか手持ちで撮影してしまったのが映画監督のクリストファー・ノーラン。
詳細は各自検索していただけたらと思いますが、バットマン3部作やダンケルク、インターステラーといった作品でIMAXカメラは大いに活用され、プロレスラーのような体格の撮影監督ホイテ・ヴァン・ホイテマが巨大なIMAXカメラを担いで撮影しているメイキング風景には度肝を抜かれます。
デジタルではどうでしょうか。映画の世界ではARRIのALEXA 65というカメラが事実上唯一のOver35mmフォーマットカメラではないかと思います。ALEXA 65のセンサーサイズは54.12×25.59mmとかなり横長のサイズ。GFX100 IIのセンサーが43.8×32.9mmですから、横幅では負けても高さでは勝っています。動画なら上下は少し切れますが、それでもかなり近い線を行っているのです。何より、ALEXA 65は世界でもレンタルでしか手に入らない激レアカメラ。重さも本体だけで10kg超えですからハンドリングは比較になりません。
閑話休題。私がGFXシリーズで動画を撮影できることに興奮を覚えるのは、まさにこの、35mmフルフレームを超えたフォーマットでの動画撮影という本当にごく限られた機材でしか実現できなかったものが極めてリーズナブルに手の中に収まるサイズで実現できているという、その1点に集約されているといっても過言ではないわけです。もう少しシンプルにいうと「ロマン」です。
外観をチェック
最初にお伝えした方がいいかと思うのは、今回のレビューではいわゆるリグを組んでのシネマセッティングはしていません。このカメラのキャラクターを考慮した結果、あまり余計な周辺機器を付けずにボディとレンズのみでシンプルに使った方が良さそうだと思ったからです。後述するいくつかのネガティブポイントもその理由だったりします。
さて、カメラの外観をチェックしてみたいと思います。先代GFX100との1番の違いは、ボディ下部のグリップがなくなり、GFX100Sを思わせるすっきりとしたシルエットになったという点。グリップ一体型ボディもプロ機っぽさがありましたが、同じ性能なら軽くて小さい方がいいに決まっています。


側面。チタンをイメージさせる独特な硬質感のある表面加工も健在です。直線的なボディラインが高級感を醸し出しています。

個人的にはこの斜め後ろからのボディラインが、上面液晶が斜めにカットされたスタイルと相まってものすごく「中判っぽくてかっこいい」と思いました。


端子類。極めてシンプルで、イーサネット、マイク端子、フルサイズHDMI、USB-C。マイク端子はLANC端子兼用とのこと。反対側にイヤホン端子があります。USB-C端子から給電撮影を行うことができるというのは大きな利点です。

逆サイドのメディアスロット。使用メディアはCFexpress Type BとSDカードのダブルスロット。CFexpress Type Bは近年いろいろなメーカーが採用しており、価格もこなれてきており大容量でも比較的安価に揃えられるのがありがたい。またダブルスロットのメディアが違うというのも個人的には高評価でした。

ファインダーを取り外すとコネクターを内包したクイックシューとそれを取り囲むファインダー固定用のスライド金具があります。動画制作時にはこの状態で運用した方がいろいろ使い勝手が良さそうですが、ファインダーの見え方は非常に良いので、手持ち撮影ならファインダーをつけて運用するのもいいかなと思いました。

カメラ上面から。モードダイヤルの前にあるムービーとスチルの切り替えボタンでオペレーションが変わりますが、切り替え時間が非常に高速なのが素晴らしい。ちなみに設定を切り替えてもシャッタースピード、感度、絞りといった撮影設定は引き継がれず、ムービー用、スチル用で別々に保存されているようです。
例えばスチルで設定を詰めながらちょっとだけムービーを回したい、みたいな使い方をしようとしても、それぞれのモードで設定をし直さないといけないので注意が必要です。
ボディデザインについて感じることは、先代GFX100を継承した直線的で硬質感のあるデザインであること。ソリッドな質感と持ちやすさが両立した、他にないデザインだと感じました。反面、端子の数は必要最低限で拡張性よりもデザインを優先した印象を受けました。この辺りも、このカメラを素のままで使おうと思った理由です。
HDMI出力信号をチェック

今回、HDMI経由でのBlackmagic RAWも検証したかったのですが、執筆時点ではまだ対応しておらず(2023年9月26日のVideo Assist 3.13 アップデートで対応)、今回はRAWの画質は見送ることに。
その代わり、モニタリング環境のチェックを行いましたが、注意すべきポイントがいくつかあり、
- ライブ出力時は収録中の解像度、フレームレートで出力されるが、再生時は強制的に2160/59.94pに変換されてしまう
- 再生出力時はモニタリングのアシストが外れてFlog/Flog2のままになってしまう(Flog/Flog2で撮影した場合)
- 出力のフォーマットを選択することができない
- 再生出力時、本体モニターはブラックアウトしてしまう
など、クライアント向けに常にモニター出ししながらこのカメラを使うのはいくつか改善してほしい点を感じました。
自分だけで本体モニターでオペレートする分には気にならない部分なので、その辺りは割り切って使用する方が良さそうだと感じました。


純正アクセサリとして、センサーの冷却を行う「FAN-001」があります。取り付けてみましたが液晶の可動に結構制限が出る模様。ちなみに今回は使用せず9月の日中で半日ほど撮影しましたが、警告が出ることもありませんでした。
4K?8K?画質のベストチョイスは?
GFX100 IIは動画の収録形態も非常にバリエーションに富んでいます。詳細は公式HPを確認していただければと思いますが、以下の通りです。
■GFX100 II 主な記録画素数
- 8K 17:9(8192×4320pix)
- 8K 16:9(7680×4320pix)
- 5.8K 2.35:1(5824×2476pix)
- 4K 17:9(4096×2160pix)
- 4K 16:9(3840×2160pix)
それぞれにフレームレート、記録方式としてApple ProRes 422 HQや、H.265、H.264等のコーデックを選択することができます。
なお、公式HPのスペックシートには5.4K 17:9や4.8K 3:2等の解像度も書かれているのですが、メニューから見つけることができなかったので今後実装されるのでしょうか?
今回、「自分が仕事に使うなら最も使用頻度が高そう」という観点から、8K17:9及び4K17:9について、それぞれProRes 422 HQとH.265で画質の比較を行ってみました。フレームレートは全て23.98fpsを使用しています。
ちなみに撮影素材のキャプチャについて。特に注釈がなければ感度はISO800、撮影ガンマと色域はF-log2を使用し、富士フイルム公式よりダウンロードしたGFX100 II対応のRec.709 LUTを当てたものをベースにカラコレを施しています。F-log2のみ、LUTのみの場合はその旨を補足しています。
解像度の比較
まずチャートにて8K、4Kの比較を行います。収録コーデックはProRes 422 HQ、また4Kは撮影モードとしてGFモード(GFXレンズに最適化した撮像範囲)、Premistaモード(富士フイルムのハイエンドシネマズームレンズであるPremistaのイメージサークルに合わせたモード。35mmフルフレームより広い)、35mmフィルムモードの3つのセンサーモードを使用しました。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
まず、8Kモードの撮像範囲は「等倍クロップ」となるため事実上ほぼ35mmフルフレームとなってしまいます。これが正直なところ今回のテストで最も残念な点でした。なぜなら35mmフルフレームであればこのカメラ以外の選択肢は数多くあり、最大のアピールポイントであるフルフレーム以上の撮像面積を生かすことができなくなってしまうからです。この時点で自分の中では頭を切り替え、メインの解像度は4K、GFモードとしてより大きな撮像面積による画質を活かす方向を検証することにしました。
次に、実景を撮影して4K GFモード、8KクロップモードそれぞれでProRes 422 HQとH.265での画質を比較してみることにします。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
等倍拡大で見ていて思いましたが結構空気の揺らぎが出てしまっているので圧縮ノイズとの違いがわかりづらくなってしまいました(汗)。
まずなんといっても8Kの解像度には驚かされます。願わくは、この画質をGFXフルフレーム動画で見てみたいものです。
4Kの方は、撮像面積の大きさからくる画面の情報量があるように見えました。また、ProRes 422 HQとH.265も結構違います。天気の変化はありましたが、それでもH.265で圧縮した方はProRes 422 HQよりも明らかに色が浅くなり(カラコレは同じ設定です)、また緑の標識をチェックすると色再現で若干劣っていることがわかります。
細部を見ると、4KではProRes 422 HQ、H.265の両方で若干輪郭強調がかかっていますが、これはカメラ内のダウンコンバート処理によるものだと思われます。
絶対的な画質で最も良い結果が得られたのは、8K ProRes 422 HQ、ついで4K ProRes 422 HQだと私は思いました。このカメラを使って動画撮影をする人が撮像面積よりも画質を最重要視するのであれば、内部収録に限定すれば8K ProRes 422 HQがベストチョイスだと思います。
感度、ローリングシャッター、ラチチュード(露出耐性)のテスト
GFX100 IIの動画モードには「Dレンジ優先」モードがあります。これは、写真機能における「DR100」「DR400」とはやや呼び方が異なり、Flog-2で4K撮影をした時のみ有効になる機能とのことで「ローリングシャッター現象が見える場合があります」との注釈があります。ちょっとテストしてみましょう。ちなみにデフォルトでは「OFF」になっています。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
ノーマル露出ではあまり違いは感じられません。続いて、カメラを雲台を軸に左右に振ってみます。手作業なので速度はばらつきがありますが、なるべく同じようになるようにしています。


まあ手作業ではありますが、違いは明確に出たのではないかと思います。
しかしながら、手ブレによるローリングシャッターをどこまで嫌うかというのも個人差かと思います。少し前ならローリングシャッターによる像の歪みは「コンニャク」現象などと呼ばれて嫌われていましたが、近年センサーの読み出し速度は大いに向上しました。GFX100 IIも、それだけを取り出して比較すれば違いは出るかもしれませんが、これをもって断じるというのはあまりに早計というもの。
続けて、ダイナミックレンジを比較するべく露出をオーバーにした比較を行ってみます。オーバー露出で撮影したのち、DaVinci上でノーマル露出のチャートと同等になるように手動でカラーホイールを使って戻す作業を行いました。
まずは2絞り分、4倍の露出オーバーです。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
これではほとんど違いはわかりません。続いて4絞り分、16倍です。

※画像をクリックして拡大
16倍の露出オーバーを戻そうとしたところ、絵が破綻してしまいました。グレーの階調は比較的保たれているように思えるのですが、露出オーバーに由来すると思われる色飽和が顕著に発生してしまい、カラーがめちゃくちゃになる結果に。
続いて、DR優先をONにしたものです。

グレーの階調、チャートの色が驚くほど保たれているのがわかります。ローリングシャッターを気にしないのであれば、DR優先モードはオーバー露出に対して非常に強力な武器になると感じました。
それから高感度のテストです。GFX100 IIの常用感度は最高12800となっています。6400、12800のそれぞれでDR優先ON、OFFを比較してみました。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
ISO6400ではほとんど違いはわかりません。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大
ISO12800では、DR優先はONの方がややノイズの少ない画像になる傾向があるように見えました。しかしながらチャート上で目立つノイズを感じることはなく、センサーの持つポテンシャルの高さには非常に驚かされます。
作例
今回、仕事では投入する機会がなかったため、当初のコンセプトに忠実にボディとレンズ、それに三脚で街に繰り出してみました。手持ちも試したのですが、自然と三脚に据えてじっくり撮るスタイルの方が馴染んで行ったのは個人的にも不思議な変化。ラージフォーマットでアングルを切っていると、自然と腰を落ち着けた撮影スタイルになっていくのかもしれません。撮影は全てGFモードの4K。設定はH.265やProRes 422 HQを切り替えてみましたが、撮影後の編集のしやすさでもProRes 422 HQの方が上だと感じました。
グレーディングの感想としては、とにかく彩度が高く色飽和を起こしやすいので注意が必要ということです。赤や緑などの原色が明るすぎる時は彩度を落とすか、Davinciのカーブ機能で色相と輝度を少し下げてやると色が出てくるようです。暗部を少し転ばせるとちょっとポジのような風合いになりますが、いわゆる「写真画質」で、ETERNAのLUTを当ててもいわゆるシネマ的なルックにするのは難しい印象でした。写真として見ると非常に綺麗なんですけどね。センサーの地力とF-log2のポテンシャルは非常に高いと思いました。






最後に
今回GFX100 IIを持ち出して一番意識したことは、中判カメラの画質でフットワーク軽くやりたいという点でした。なので普段仕事でセットアップするような外付けモニターやバッテリー、マウントアダプターでのシネマレンズなどは使用せずにカメラ本体とGFレンズの最小構成で街中をスナップしてみたのですが、「そういう使い方」をするのであればこのカメラはとても頼もしく応えてくれると思います。
しかし、リグを組んだり、ファンをつけて長時間収録に臨んだり、8Kで35mmフルフレームの映像を「仕事で」撮るのであれば、正直なところ他にもっと「向いてる」選択肢はたくさんあると思いました。今やシネマカメラは本格的なものが50万円以下でも手に入るのですから、わざわざこのカメラに手を出すことはないかと思いました。あくまでもGFXのラージセンサーという、このカメラでしか得られない世界を切り取るのがあるべき使い方だと思うのです。
このカメラは大型映像ロマンをほんの少し垣間見させてくれる「スーパーシネマティックカメラ」と呼ぶのがふさわしいのではないかと思いました。
最後になりますが、その上で僕はこのセンサーの102メガピクセルの実力を100%吐き出した動画(もちろんRAWで!)を撮影可能な「シネマカメラ」がいつか登場することを心待ちにしています!