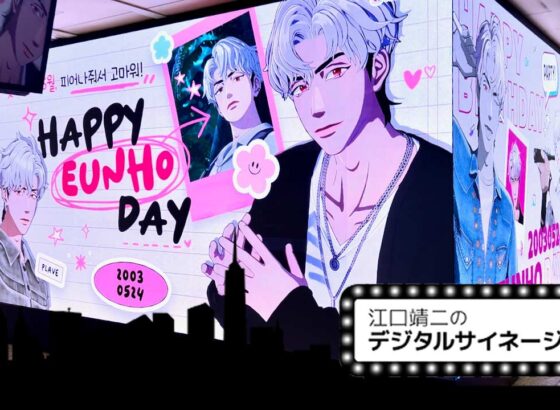デジタルサイネージの未来を考える際、音楽とアートの領域はこれまでメインストリームとは言えなかった。しかし、LEDディスプレイのコモディティー化が進む現在においては、ディスプレイの形状や用途がますます拡張され、新たな可能性が広がっている。狭くて定型のディスプレイというキャンバスから解放されることで、商業イベントや興行を超えた、よりアート性の高いインスタレーションの実現が期待される。
こうした視点から、坂本龍一(1952-2023)のインスタレーション展覧会「坂本龍一|音を視る 時を聴く」は、デジタルサイネージ関係者にとって、いま必見の内容である。
展覧会の概要
日本国内で初となる大規模な個展では、坂本龍一の大型インスタレーション作品を包括的に紹介している。坂本氏は50年以上にわたり、多彩な表現活動を展開し、90年代からはマルチメディアを駆使したライブパフォーマンスを実施してきた。2000年代以降は、音を空間に立体的に配置する試みを積極的に探求した。
本展では、坂本氏が東京都現代美術館に遺した展覧会構想を軸に、「音」と「時間」をテーマにした没入型サウンド・インスタレーション10点以上が美術館内外に展示されている。
これらの作品は、音楽鑑賞や美術鑑賞の枠を超え、鑑賞者の目と耳を開き、心を揺さぶる体験を提供する。坂本が追求した「音を空間に設置する」という芸術的挑戦や、「時間とは何か」という哲学的問いかけは、時代や空間を超えて新たな視座を提示する。インスタレーションは、高谷史郎氏をはじめとした複数のアーティストとのコラボレーションによるものである。では筆者が現地で感じたことを順にスマホにメモしていったことを素にして紹介を試みる。
デジタルサイネージへの示唆
1.時間軸のない映像コンテンツ
従来の映像コンテンツは起承転結が前提だったが、今回の作品群は始まりも終わりもないアンビエント的な構造を持つ。東京兜町のKABUTO ONE「The Heart」のように、アンビエント要素にリアルタイムデータと融合する形で、新たな視聴体験を創出する可能性を示している。
2.観覧者の時間に委ねる体験
一般的に映像や音楽は、創り手側が時間軸を規定する。しかし、今回の作品群では視聴者が自由に時間を決めることができ、時間の経過を忘れるような没入感が生まれる。デジタルサイネージ領域でも、最近イマーシブという言葉を聞くことが多いが、イマーシブとは立体視や大画面化のこととは限らない。その意味を再定義する必要があるだろう。
3.音を先行させる新たな映像体験
デジタルサイネージは従来、ロケーションの制約により音の活用が限られていた。しかし、たとえばホテルやオフィスのエントランスのような、音を使用できる環境にデジタルサイネージが拡張されていくことで、五感を刺激する新たなコンテンツ制作が可能になり、音が最も重要な情報として、映像ではなく音が先行した制作が求められていく場面が増えるだろう。
4.LEDとプロジェクターの使い分け
本展では、LEDディスプレイ、プロジェクター、小型LCDが使用されており、それぞれの特性を活かした展示が行われている。特にLEDの自己発光とプロジェクターの反射光の違いを活用し、床面の反射による空間演出が考慮されている点は、サイネージ関係者にとって興味深い示唆となる。




5.解像度の課題
視認距離が近いインスタレーションでは、現行のLED解像度では物足りなさが残る。特に500mm角のLEDユニットの施工ムラやズレが、とりわけ白くて明るい映像では目立つことが確認された。これらは、今後の技術革新によって改善が期待される。
6.「ビデオドラッグ」の時代との比較
ビジュアルコンテンツによる没入感の先駆けと言えるものの一つは、1990年に中野裕之が制作した「VIDEO DRUG」だろう。DVEによる万華鏡のようなエフェクトの映像は吸い込まれるような感覚を覚える。当時と比較すると、現代の映像は画角や解像度が飛躍的に向上している。これからの没入型映像は、脳科学やマインドフルネスとも連携し、新たな視覚・聴覚体験を創出する可能性を秘めている。
7.ナムジュン・パイクと立花ハジメの影響
坂本氏はビデオアートの父ナムジュン・パイクや、ニューウェーブ/エレクトロニックミュージックのパイオニアであり、デザインの分野でも評価の高い立花ハジメの影響が感じられる。彼らの作品は、映像と音楽を融合した表現の先駆けとして、現代のインスタレーションに大きな示唆を与えている。こうした先達の作品に対して未来を発見できるかもしれない。


8.XR的な視点
坂本氏の演奏による「Ars Electronica 1997」でのMIDIデータとその記録映像データからの再現展示である。28年前の映像を、今の時代としてはあえて「チープなテクノロジー」でクロスリアリティーさせている。
この展示では、多くの人たちが涙していた理由を私たちはしっかりと考える必要がある。先ほど解像度がまだまだ足りないと述べたが、解像度だけでは解決することはないのも事実である。

展覧会情報
「坂本龍一|音を視る 時を聴く」は、2025年3月30日(日)まで東京都現代美術館で開催。現地で当日券の購入も可能だが、オンラインでの日付指定チケットの事前購入を強くおすすめする。
WRITER PROFILE