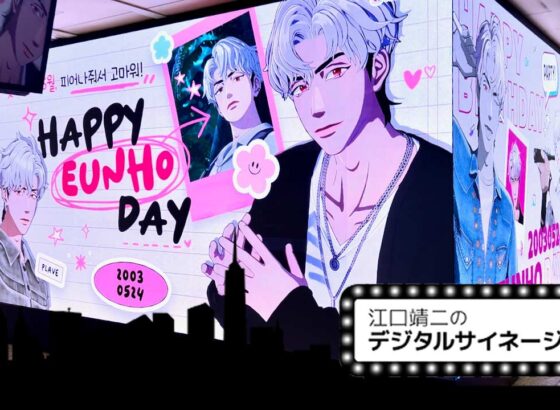txt:江口靖二 構成:編集部
デジタルサイネージは、家以外の場所に設置されたディスプレイやプロジェクターに対して、広告、販促、インフォメーションを表示するメディアのことだ。また、見方を変えると、デジタルサイネージは街に飛び出すインターネットであるともいえる。ここでいうインターネットはWebと言い換えてもいい。
これまでパソコンの画面の中だけで閉じこもっていたWeb、またはWebサービス、Webビジネスを街中に引っ張りだすことができるのがデジタルサイネージなのだ。これは家と街中では場所が異なることによる接触態度の違いがあり、これらは相互補完できる関係にある。あるいはそうなるべきだということだ。人は一日中パソコンの画面に張り付いているわけではない。ということはパソコンを見られない状態は、Webビジネスにとっては機会損失である。スマホは一定量これらを穴埋めするが、やはり歩きスマホには限界がある。
たとえば明日の天気を知りたければ、天気予報サイトにアクセスすればいい。これは能動的な意思があるのでこれでいいが、明日の天気はわざわざ調べなくても、生活の中で知らず知らずにわかったほうがありがたい。テレビの画面の片隅の天気マークも、街中のデジタルサイネージの天気予報も、わたしたちの生活動線の中で知らず知らずに視界に入り、認知されている。時計(時刻)もこれに近い。
SNSとデジタルサイネージの連携とは
このようなインターネットビジネスのリアルへの進出が、デジタルサイネージの重要な側面なのだが、インターネットでいまビジネス的に注目を集めているのが、言うまでもなくSNSだ。そこでSNSとデジタルサイネージの連携が日米で昨年の秋くらいから注目を集めている。特にInstagramやPinterestなどとの連携だ。
■Enplug
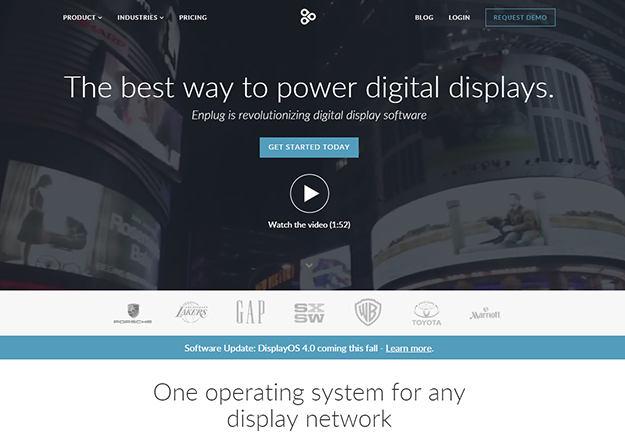
その一つが今年の3月に米・ラスベガスにて開催された「Digital Signage Expo」で初めて目にしたロサンゼルスの「Enplug」だ。
もともと成立しているInstagram、Twitter、FacebookなどのSNSをサイネージ用に表示させるというもの。表示に際しては当然SNSのデフォルトの状態ではデザインやレイアウト、文字サイズなどがデジタルサイネージには適切ではない。そこで公開されているAPIなどを利用して、デジタルサイネージ用に表示をしなおしているわけだ。
このようにSNSをデジタルサイネージに使うメリットは非常に多く存在する。まずコミュニケーション視点では、もともとオンラインでのコミュニケーションが成立しているものの、オフラインへのエクステンション(拡大)であるということだ。またコスト運用面でもメリットが大きい。新たにサイネージのためにコンテンツを制作することも、CMSを設置する必要もない。制作費も運用費も0円である。端末側も表示はブラウザだけでよいのでやはり超低コストだ。もちろん表示する映像の詳細なプログラミング(編成)ができないなどの制約はあるが、相当数のデジタルサイネージの実際の運用から見ると、これで必要十分であるのではないだろうか。
■TINT

類似のサービスとしては、Enplugと同様にカリフォルニアベースの「TINT」がある。こちらはどちらかと言うと常設のデジタルサイネージというよりは、イベント会場等での画面の共有というか、サイネージだけ単独でメディアとして成立させようという方向性は薄いようだ。
■SocialScreen

さらに「SocialScreen」というサービスは、カンファレンスでの特定ハッシュタグの表示や、個人での特定のフィードの表示といったものを指向しているようだ。Web時代的に言うなら、RSSの自動表示といったところで、パーソナルサイネージの領域だ。
■FLOW
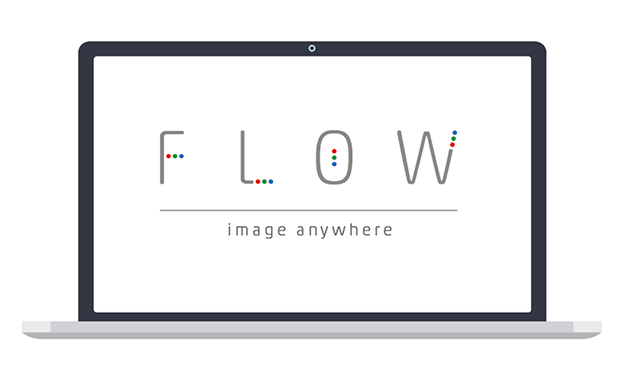
こうしたSNSとデジタルサイネージの融合は、アメリカだけではなく日本でも動きを見せはじめている。日本のインセクト・マイクロエージェンシーが「FLOW」というサービスをスタートさせている。すでに大手ファッションブランドなどとの実績があるという。
■C CHANNEL

また、少し異なるアプローチをはじめたのが「C CHANNEL」だ。これは若い女性向けに特化した動画ファッションマガジンというポジショニングのメディアだ。クリッパーと呼ばれる女性レポーターのスマホで撮影した縦動画が基本。縦の画角を生かして今後はデジタルサイネージへのコンテンツ展開を進めていくようだ。7月13日からは名古屋の屋外ビジョンへの配信がスタートした。なおC CHANNELは、元LINE会長の森川氏が個人でのスタートアップである。
総括
マーケティング的には、これらは広告とも販促とも異なるポジショニングになっていくに違いない。従来型のデジタルサイネージ、特に交通広告などのような既存のアナログ広告のデジタル化によってビジネスが拡大している部分の話と、ソーシャルスクリーン化の話は、成り立ちもビジネスモデルも異なるのでおそらくは相容れない別の動きになっていくだろう。SNS側もデジタルサイネージ側をきちんと理解した上で、互いの領域拡大を目指していきたいと思う。
WRITER PROFILE