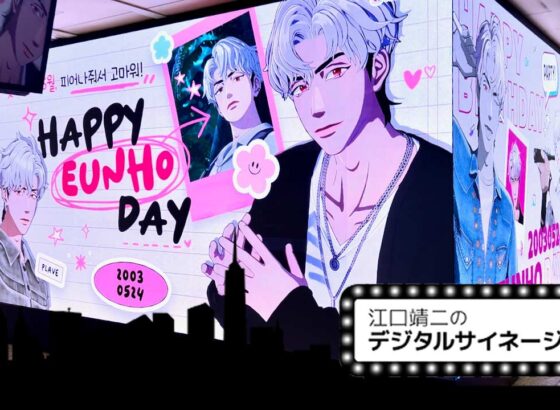デジタルサイネージの利用法の一つにはアンビエントやアート的なものも含まれる。デジタルサイネージのすべてが純粋アート作品ではないにせよ、その表現手法においてデジタルアートから学ぶことは少なくはない。そこでいま開催中の参考となる2つのデジタルアート事例を紹介する。
事例1:「ファン・ゴッホ」展
最初に紹介するのは、11月27日まで角川武蔵野ミュージアムで開催中の「ファン・ゴッホ -僕には世界がこう見える-」だ。この展示は現在北米20カ所で開催されている「The Original Immersive Van Gogh Exhibit Created By Massimiliano Sinccardi」の日本初上陸版である。邦題がなぜこうなるのかよくわからないが、筆者は先日ラスベガスとロサンゼルスで見損なったので、こうして日本で体験できるのはとてもありがたい。
これはゴッホの世界観を映像体験することができるデジタルアートだ。ゴッホの作品をアニメーションやコラージュでホールの壁4面と床面にプロジェクターで投影する、没入型の作品である。

ここで最初に気になったのが、プロジェクターで投影される解像度、輝度、彩度のどれもが期待を下回ることだ。今の技術では、膨大な数の高輝度プロジェクターを持ち込まないと無理であることが露呈する。会場のプロジェクション(マッピングはしていない単純投影)環境を見ても、特に鏡の使い方、そのエッジ部分の使い方が雑だと感じた。
今回使用されているゴッホの作品の現物を何点も見たことがあるが、これでは現物の作品を超えられてない。しかし、これがデジタルの限界ではないはずだ。例えばチームラボのデジタルアートは、基本的に本物が存在していない、チームラボのデジタル作品がオリジナルだ。そのため、プロジェクターの暗くて眠たい映像でもデジタルアートとして成立し、新たな価値を見る者に提供している。
また、会場には常に何らかの音楽が流れているのも気になった。ゴッホの作品と向き合う時に、時間軸を音楽に持っていかれたくはない。自分のタイミングで感じたいと思うのが普通ではないだろうか。これならNHKの番組「日曜美術館」のような、いい意味で完全押しつけの完パケコンテンツの方がずっといい。
しかしながら、スマホやデジカメで撮ると、現場で肉眼で見るよりも遥かに明るく鮮やかに撮影できる。とてもSNS映えするのは間違いない。「SNS映えまで設計するのが今のデジタルアートだ」、というなら返す言葉はない。
没入という意味では、原作を遥かに超えたサイズで体感できることは確かであるが、果たしてそれが適切な手法なのだろうか。たとえば「鳥獣戯画」を同様に動かし、着色したらどうなのか。そんなことを想像しながら、ぜひ実際に体験して考えてみていただきたい。
事例2:Digital×「北斎」特別展
もう一つは北斎である。
初台のNTTインターコミュニケーション・センター(ICC)で7月3日まで開催中の「[Digital×北斎特別展]大鳳凰図転生物語 小布施とHOKUSAI 神妙に達していた絵師」は、アナログアートをデジタルで見事に昇華させた好例だ。
ちなみに、北斎の作品自体には筆者は特段の興味はない。強い関心を持って体験をしようと思ったのは、アナログアートに対してデジタルは何ができるのかという問題意識だ。北斎の天井絵がアートかどうかはともかく、本物の天井絵を超高精細デジタルスキャンし、圧倒的な緻密さと正確さで再現している。その再現方法はディスプレイやプロジェクターではなく、プリント出力というのもとても重要な部分だ。

会場入り口正面に展示されているものは、垂直に壁にかかっていた。これは展示方法として違うと思ったのだが、会場奥では岩松院の空間をプロジェクターで再現しながら天井に水平に天井絵として設置し、さらに極楽浄土の世界観を映像で再現する手法であった。


もう少し詳細に説明すると、正面の展示は緻密に再現されたマスターレプリカの精度を確認することができるもので、奥の展示はもう一つレプリカを出力し、本来は背景に金箔が貼られていたであろうという説を元に、現物とは異なる想像の作品の再現として展示されている。現物に金箔を貼るわけにはいかないが、デジタルレプリカなら可能だからだ。
また最終表現、最終出力をディスプレイやプロジェクターを用いるのではなく、最後は印刷なのである。ゴッホの例はアナログをデジタル化して、デジタルとして表示しているのに対して、北斎の方はアナログをデジタルを介してアナログに出力するという異なるプロセスなのである。
最先端技術で忠実なマスターレプリカを作り、それに対して現場ではできないデジタル演出をするというのはとても良いのではないか。ゴッホの例も、もしかすると現物がそこにあって、その上でデジタルで創造性を拡張することに特化すれば話は違うかもしれない。実際にはレーザー光を絵の具に当てるわけにはいかないので、それは不可能であるが。他には天井絵と絵画は表現としては全く別の物という相違点もあるだろう。
デジタルで本物があるものを再現しようとした瞬間、解像度だけでなく本物の質感も伝えられないのであれば、それは劣化でしかない。これら2つの異なる事例は、技術的な押し付けではなく、ユーザーに「意味があるのか?」を考えさせる良い機会だと思う。
- 会期:2022年6月18日(土)~11月27日(日)
- 会場:角川武蔵野ミュージアム1階 グランドギャラリー
[Digital×北斎特別展]大鳳凰図転生物語 小布施とHOKUSAI 神妙に達していた絵師
- 会期:2022年6月2日(木)~7月3日(日)の木~日曜日に開催
- 会場:NTTインターコミュニケーション・センター (ICC)ギャラリーA
※事前予約が必要
WRITER PROFILE