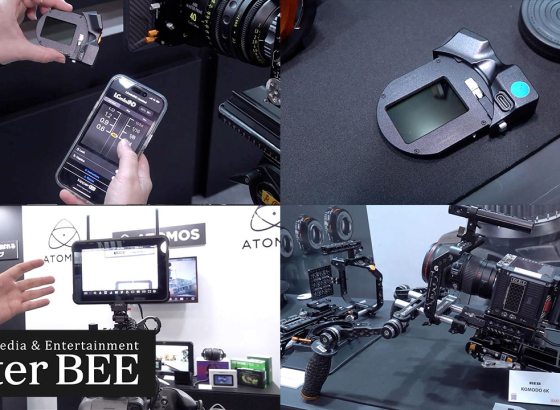機材の進化はカメラ本体だけではない。今年のInter BEEにおいて、筆者が特に圧倒されたのが三脚・一脚カテゴリにおける技術革新だ。Vinten、Sachtler、Manfrotto、Libec、SmallRig、そしてYC Onion。これらのブースで目撃したのは、セットアップの「高速化」や縦位置動画への対応、そして不整地での即応性といった、現代の撮影現場が抱える課題への鮮やかなソリューションであった。もはや三脚は単なる支持機材の枠を超え、映像制作の質とスピードを左右するデバイスへと進化している。その最前線を詳細に解説したい。
Vinten・Sachtler・Manfrottoが提示した「現場の悩みを技術でねじ伏せる」進化とは
ヴィデンダム・プロダクション・ソリューションズのブースを訪れ、三脚という機材が単なる「カメラを支える道具」から、撮影のワークフローを劇的に変えるデバイスへと進化している事実に、圧倒された。Vinten、Sachtler、Manfrottoという業界を牽引するハイブランドが一堂に会するこの場所で目にしたのは、長年の現場の悩みを技術でねじ伏せるような回答の数々だったからだ。
まず驚かされたのが、Vintenの新型ヘッド「Versine 240」である。昨年登場したモデルの小型版とのことだが、特筆すべきは「ペイロード範囲:0~25kg」という守備範囲の広さだ。通常、大型の放送用ヘッドといえばある程度の重量を載せなければバランスが取れないものだが、この製品はカメラを載せていない状態、つまり0kgでもVinten特有の「パーフェクトバランス」が機能するという。
GoProのようなアクションカムから本格的なシネマカメラまで、ダイヤル操作一つで完璧に対応できる柔軟性は、機材選択の常識を覆すものだ。また、海外のトレンドに合わせて短めに設計されたパンバーや、搬入出を考慮した吊り上げ用の穴など、実用性を徹底的に突き詰めた設計には感服した。

続いてSachtlerの展示も大注目だった。「aktiv」シリーズに新たに加わった100mm径の高耐荷重モデルは、セットアップの概念を変えるものであった。従来、三脚の水平出しや脱着といえば、ヘッドの下からネジを回す煩わしい作業が必須だったが、このシリーズはレバー操作のみで瞬時に着脱が可能である。この「爆速」とも言えるセットアップ速度は、一分一秒を争う現場では強力な武器になるだろう。

さらに興味深かったのが、カーボン脚「flowtech」との組み合わせによる運用だ。スプレッダーを外して脚を広げれば、ハイハット(超低アングル用三脚)を使わずとも地面すれすれのローアングル撮影が可能となる。機材を減らしつつ表現の幅を広げられる点は、ワンマンオペレーションの多い現代の撮影事情に合致している。また、水準器を正面から光らせて確認できる「PrismBubble」も、背の低い撮影者や高い位置へのセッティング時に威力を発揮する、地味ながらも極めて実用的な「発明」だと感じた。

Manfrottoのハイブリッド三脚システム「Manfrotto ONE」も、時代の空気を敏感に捉えていた。写真用三脚のフォルムでありながら、ビデオ雲台としての機能を持ち、あまつさえ「縦位置動画」に対応している点は慧眼である。「Xchange」システムにより、フォト用雲台とビデオ用雲台を瞬時に交換できる機構は、スチルとムービーの垣根を超えて活動するクリエイターにとって福音となるだろう。ヴィデンダムのブース全体を通して見せつけられたのは、単なるスペックの向上ではなく、「いかに現場のストレスを減らし、撮影に集中させるか」という思想の具現化であった。

強化された「NH」ヘッドや、機動力を変える小型三脚「TK-210C」の実力
「現場のストレスを減らし、撮影に集中」という思想は、日本のメーカーである平和精機工業/Libecのブースでも強く感じられた。まず初お披露目となった「TH-650X」の展示には、良い意味で裏切られた。
重量2.7kgという小型軽量モデルだが、「写真機材で動画も撮りたい」という層を明確にターゲットに据え、ビデオ三脚としては珍しく「アルカスイス互換プレート」を標準採用している点は極めて実用的であり、トレンドを的確に捉えている。フリクションコントロールとロックが一体化したシームレスなヘッド操作や、指のかかりが良い脚ロックなど、実売2万円以下が予想されるエントリーモデル市場に対するLibecの並々ならぬ「本気」を感じずにはいられない製品だった。

一方、プロユースラインの進化も見逃せない。ビデオヘッドの新製品「NH20」および「NH40」は、一見すると既存モデルのマイナーチェンジに思えるが、実際に触れてみるとその進化の深さに驚かされた。特筆すべきはロック機構の徹底的な強化である。内部素材から見直すことで固定力が大幅に向上しており、パンやティルトの操作形状もより扱いやすく洗練されていた。ダイヤル操作に追加されたクリック感など、派手なスペック競争とは一線を画し、道具としての信頼性を突き詰めた姿勢には好感が持てる。

同時に展示されていたカーボン製クイックロック三脚「QL40C」も興味深い製品だった。昨年のアルミモデル「QL40B」をベースにカーボン化した製品だが、最大高をあえて約151cmに抑える代わりに、最低高を38.5cmまで下げられるよう設計変更されている。高さを犠牲にしてでも、卓上撮影やローアングル時の安定性を優先したという割り切りは、制作現場のリアルな需要を捉えており英断だと感じた。

さらに、「タンキャク」というユニークな通称で親しまれているベビー三脚の新製品「TK-210C」にも驚かされた。小型ながら耐荷重が40kgに設定されており、プロの現場で用いられる重量級の機材を余裕で支える堅牢性を備えている。これ一台あれば、ハイハット的な用途から通常の低位置撮影まで柔軟に対応できるため、現場の機動力を高める強力なツールになると確信した。

ハンドルを握るだけで準備完了。設置から撤収までを極限まで短縮した、SmallRigの「爆速」機動力に驚く
機動力という点では、SmallRigブースにおける2025年モデルの三脚展示も群を抜いていた。特筆すべきは、ハンドルを握るというたった一つの動作で全脚の伸縮操作が完結する点だ。さらに興味深かったのは不整地での適応能力である。階段のような段差がある場所でも、脚の長さを個別に微調整する必要が一切ない。ただ置くだけで、システムが地形に合わせて瞬時に水平を出してくれる様子は、三脚の常識を覆す光景だった。設置から撤収までのプロセスを極限まで短縮したこの一本は、スピードが命となる撮影現場において強力な武器になるだろう。

その名は「Tako」。ペダル操作からモジュラー変身まで、一脚の常識を斜め上に超えていく意欲作
最後に、YC Onionブースにおける新型一脚「Tako」の展示も、独創的なギミックの数々に驚かされた。特に目を引いたのは足元の三脚ベース部分だ。ペダルを踏むだけでポールの角度調整から垂直ロックまで完結する操作感は極めて直感的であった。さらに興味深かったのが、ポールを取り外して専用パーツに換装すれば、ライトスタンドとしても運用可能というモジュラー設計だ。雲台に関してもボタン一つで縦位置撮影への切り替えが可能になっており、単なる「カメラを支える棒」ではなく、クリエイターの機動力を最大化する多機能ツールとして、非常に完成度の高い製品だと感じた。

今回の展示会取材を通して、三脚という成熟したジャンルにおいて、まだこれほどの進化の余地があったことに、清々しいほどの驚きを覚えた。各社とも、スペック上の数値よりも「現場での体験」をどう向上させるかに注力しており、映像制作の未来がより自由で快適なものになることを予感させる充実した内容であった。